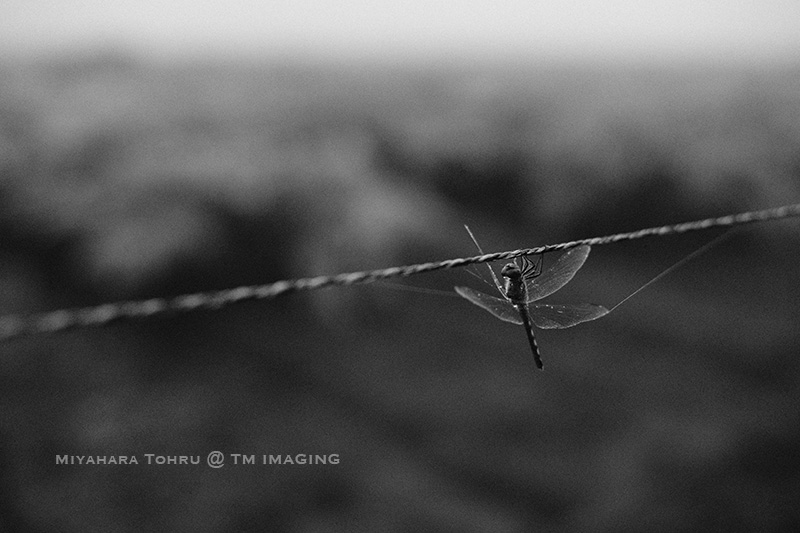fpを阻むものそれはローガン
シグマfpは結構売れているようで、α7SやGH5には興味を示さなかった仕事仲間が手を出していると知ってやや驚き。そして購入者に共通しているのがメイン機ではなくあくまでサブ機としての購入というやつで、中には完全に趣味のYouTube動画用にという輩もいた。
発売直後ということもあるが実売で20万近くしてGH5より高いのだが、世界最小の35mmフルサイズシネマカメラ..メーカーコンセプトはポケッタブル・フルフレーム..というコンセプトに映像クリエイターたちは心惹かれるものがあるのだろう。
これでセールス的にパナのS1系より売れていたらシグマの笑いが止まらないところだが、fpのプチヒットのおかげでLマウントのシェアが微増したのは間違いないw
かくいう拙者もfpは検討している最中たが、コンパクトな運用状態ではファインダーが無いのが辛い。動画撮影時は三脚運用なので問題ないだが、写真撮影時にはEVFで良いのでやはりファインダーが欲しいと、老眼オヤジは常々思うのである。fpには別付けのLCDビューファインダーが用意されているが、さすがにアレでは「ポケッタブル」とは言い難く、写真撮影にも使いたい身としては悩ましい話なのだ。
実はGR3を躊躇している理由もそこだったりするw 若き頃に初代GR DIGITALを使っていた頃は眼前のモニターが見えていたのだが、寄る年波には勝てず、近年は老眼が進行してメガネを外さないと手元はよく見えないw
当然スマホもメガネを外さないと見えないのだが、スマホやタブレットを眺める時はその行為自体が目的となるので、メガネを外す..正確には額に移動するだが..事に支障はないが、撮影時はファインダー代わりの背面モニターと被写体や周囲とを見比べることになるので、そこがイチイチ面倒なのである。
一応試しに遠近両用メガネも使ってみてはいるが、視線移動の少ない運転時以外はちょっと常用する気にならない。
以上、fpのネタ話にかこつけたが、オヤジカメラマンにとってローガンとの戦いは未だ止むことがないのであるw
錦繍の奥利根のブナの森。やはり県内の紅葉は10日近く遅れている感じで、先週の時点でまだ坤六峠周辺が見頃だった。
やたら雨の多い秋なので色づきを心配したが、今年はまあまあではないだろうか。