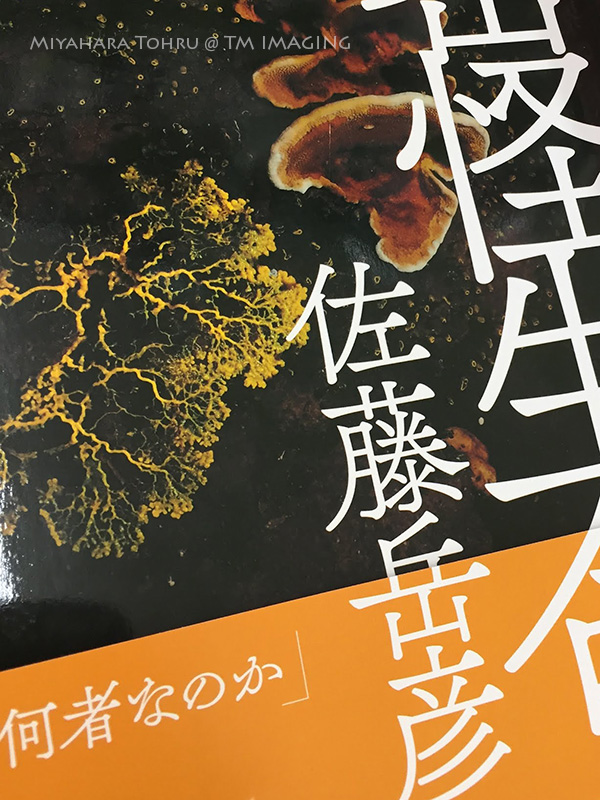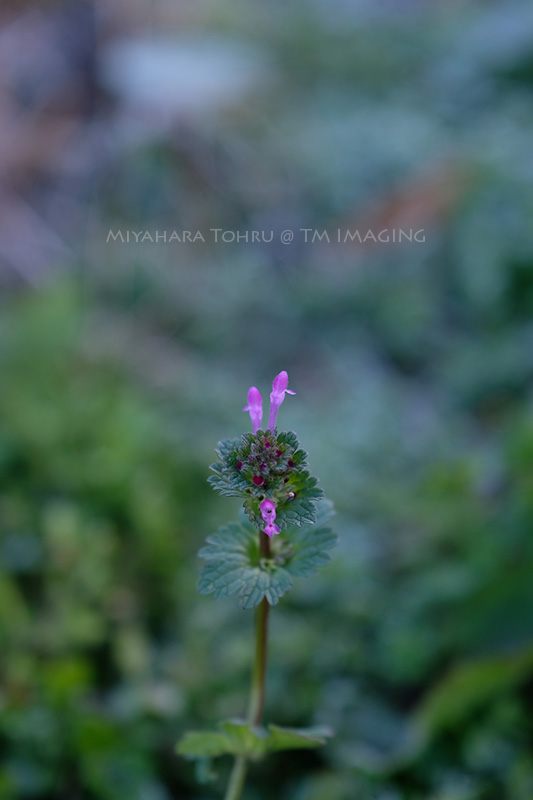新興中華侮りがたし
某社の新型カメラの企画会議で、次にカメラに搭載する新たな機能について意見を募ったところ、「電話機能を付ければ撮ったその場からすぐに写真を送れます!」と真顔で意見具申をした若手がいて、それって写メじゃね?という突っ込みの笑い話は業界アルアルだ。
さて、大陸の方にEFレンズやFマウントレンズのパクリっぽい製品を作っているYongnuoという交換レンズメーカーがあるが、先日そのYongnuoから背面に交換レンズマウントを装備したスマートフォンが発表された。
韓国のサムスンが以前Galaxyのシリーズで似たような製品を出していたことがあるが、Yongnuoは交換レンズがEFマウントで、センサーはマイクロフォーサーズの1600万画素..恐らくソニーパナソニック製だろう..でしかもRAW対応、動画も4K/30Pで撮れるようだ。
個人的に、そのうちこのような仕様のスマホが作られるだろう、そしてそれは間違いなくカメラ王国の日本ではなく大陸、つまり中華製だろうとは常々思っていた。カメラメーカーに限った話ではないが、今や日本のメーカー各社にこのような発想..というより企画と実行の迅速な判断..は不可能と言って良いだろう。
ところで、Yongnuoの製品で注目すべきは、カメラ本体がいわゆるAndroidスマホである点である。OSがNougat(Android 7.1)なので、JavaでEFレンズ..できればマイクロフォーサーズマウントを希望したい..を操作するカメラアプリを自前で開発できるということになる。そしてこの場合、写真より動画、つまりEFマウントのビデオカメラが自作できる点が何より面白そうだ。
もちろん曰く付き中華製なので、キヤノンとライセンス契約をしているとは到底思えずw、どこまでEFレンズを操れるのかは不明であるが、万が一にでも同社からフレームワークが公開されれば、面白いことになるなぁと妄想している次第。
以前は安かろう悪かろうだった中華製も今や完全に上と下に二極化し、ドローンの雄であるDJIを見ていれば判る通り、振興ベンチャーでフットワークの軽い分、特定分野なら上は技術立国日本を追い抜いているのは間違いない事実である。あ、Yongnuoの製品がどっちなのか知らんけどねw
この秋のフルサイズミラーレスカメラの発表ラッシュを見ていれば、カメラのミラーレス化はもはや止めようのない必然的な流れで、そうなると工業製品としては純然たるメカよりエレキ、そしてソフトウエアの重要性が増すことになる。
先日、キヤノンのEOS RやナイコンZの記事で、日本のメーカーはブランドの上にあぐらをかいた製品しか出せないと書いたが、両社がミラーを高速でバタバタ動かすことで競ってきた技術など、もはやレガシーまっしぐらということだ。
日の出直後、三峰に虹がかかった。冬型が強まりだす晩秋によく見られる光景だが、気温の方は相変わらず低くない。