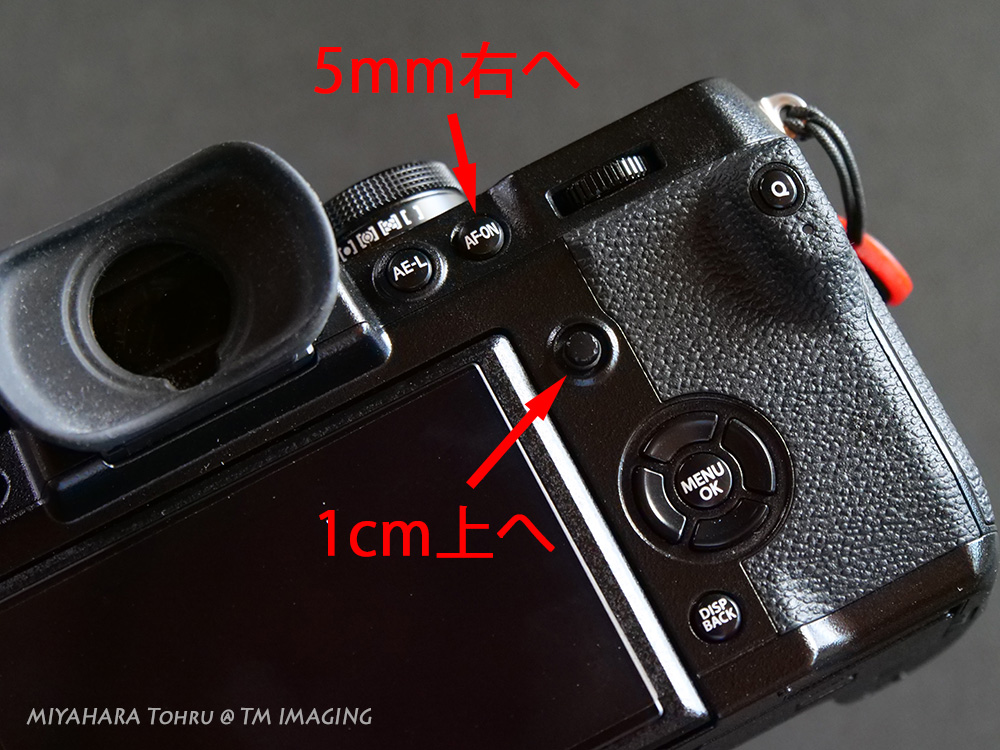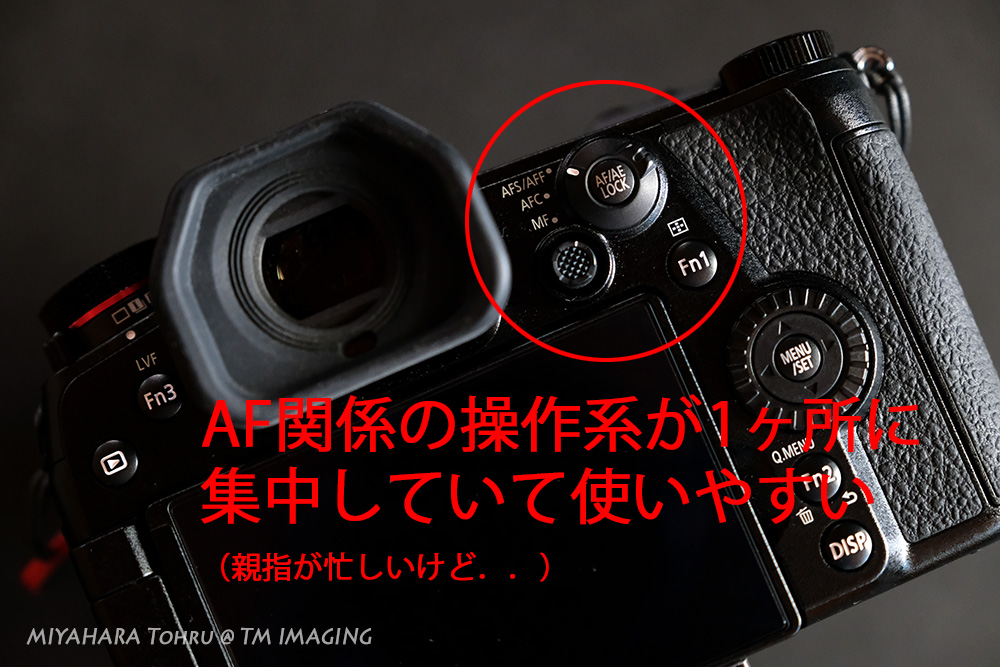X-H1のセールスポイントの一つは、Xシリーズ初のボディ内手ブレ補正(IBIS)であろう。すでにオリやペンタやソニー、最近ではパナもIBISを搭載したモデルを用意しているため、それ自体に目新しさはなく、むしろ自由度の高いはずのミラーレス機では周回遅れの感漂うフジであった。
ミラーレス一眼のメーカーとしてやや後発であること、当初は画質優先を謳って手ブレ補正に懐疑的な発言をしていること、コンシューマではなくプロシューマを目指すモデルで初めて実装してきた..営業的には写真のビギナーにこそ訴求力が高い..辺りに、フジの自信の程が伺えるというものだ。
撮影時の手ブレの原因はシャッター速度が遅いというのが最も大きい要因だが、それを逆手に取って意図的に撮影結果に織り込む手法もある。で、実際のフィールドでスローシャッターを使う場面と言えば、星景写真のような長時間露光を除けば、水の流れや滝などの流動感を表現するケースだろう。
今までならそんな時はさすがに三脚のお世話にならざるを得なかったのだが、先日来、いくつかの場面でX-H1のIBISの威力を試したところ、広角レンズ使用時にシャッター速度が1秒以下であれば、かなり歩留まりよくIBISだけで対応できることが判った。

FUJIFILM X-H1 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR

FUJIFILM X-H1 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR
まずは1/15秒の例。日中でNDフィルタなしだと、どんなに絞り込んでも1/15秒辺りが下限であるが、この程度だと望遠レンズでもレンズ内手ブレ補正であればさほど問題ではないだろう。
FUJIFILM X-H1 / XF16-55mm F2.8 R LM WR
これらは木漏れ日の差すやや明るい感じの林内で、雪解け水の流れをスローシャッターで狙ったもの。ND8を装着してF22まで絞り込み、1枚目が0.3秒、5枚目が0.5秒、それ以外は1秒で撮影した。
過度な絞り込みによる回折の影響はさておき、さすがに1秒では歩留まりが5割まで下がった..ここは個人差があろう..が、それでも1秒というスローシャッターを手持ち撮影できるというのは強力な武器であろう。
今回のケースで言えば何れも三脚が使えないシチュエーションではないので、普通に考えれば三脚に固定するのが望ましいのだが、フィールドの状況や撮影アングルによってはそう上手くいかないこともあり得るので、やはりIBISの恩恵は計り知れない。
ちなみに小中大滝..表記がややこしいのだが、小中という場所にある大滝のことねw..の写真も手持ちスローシャッターによるもので、この時もND8で0.3〜1/8で撮影している。当日は時折風が吹く状況だったので、手ブレよりは被写体ブレでアウトになるケースが多かった。

それこそ長玉..いわゆる超望遠レンズのこと..を使っていた頃は三脚の使用が大前提であったが、ミラーレス一眼と高性能な手ブレ補正の登場でそれももはや過去の話だ。
動画や物撮り、それに待機を余儀なくされるようなケース..ワイルドライフ撮影でのブラインド利用とか..を除けば、デイライトでは三脚は使う機会は少ない。
風景写真を撮るなら三脚は必須ではないか?ということになるのだろうが、拙者の撮影ジャンルは風景スナップ..勝手にカテゴライズしているだけだけど..なので、三脚にカメラを載せじっくり構えてレリーズでパシャ、なんてことは基本的にやらない。あくまで速写性重視なのである。
同時に動画を撮ることがあるのも理由の一つではあるが、そもそも三脚を使う必要がない場面でいちいち脚を広げてセッティングをすること自体をナンセンスと考えているのが大きい。そのためにもレンズ内であれIBISであれ、手ブレ補正は必須なのである。