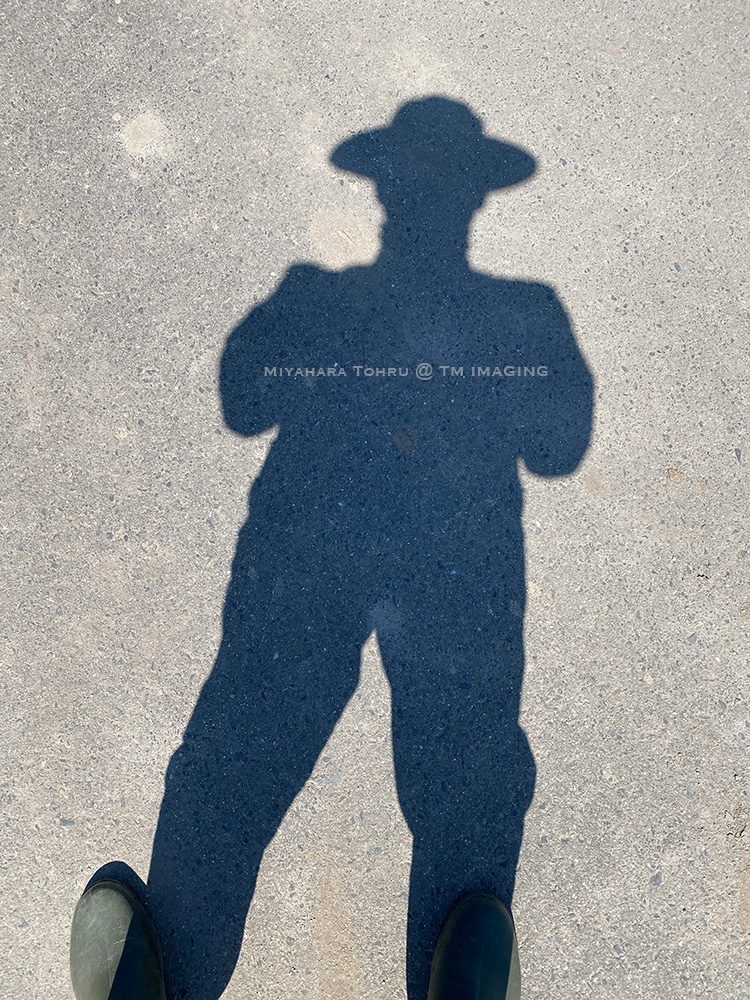梅雨の晴れ間に久しぶりに尾瀬を歩いてきた。目的は主に開発中のアプリのフィールドテストを兼ねてだが、まあそっちの話は追々。
ミズバショウが終わってニッコウキスゲにはまだ早い、そんな閑散期を狙っての行動で、その狙い通りに人出もまばらでヤマツツジが見頃を迎えた静かな尾瀬を歩くことが出来た。今回はレアな?当ブログの中の人の姿をw

iPhone SE / 尾瀬ヶ原を征く
話は逸れるが、尾瀬ヶ原の特異な景観と自然環境は置いておいて、その尾瀬の何が嫌かって、とにかくあの木道を列をなしてハイカーが賑々しく歩いている眺めである。過去、最盛期に足を運んで何度ゲンナリして帰ってきたことかw
まあそれはさておき、ついでに見たかったのはシカの食害対策の現状である。

OM-D E-M1 MarkIII / M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO / ミツガシワ
尾瀬はこの20年余りのシカの食害被害が尋常でなく、ニッコウキスゲやミツガシワがだいぶやられてしまっている。
氷河期の生き残りと言われるミツガシワなど、昔は池塘や堀..尾瀬では川を指す言葉..の周辺に多数の群落が見られたが、15年ほど前に撮影仕事で入り浸っていた頃でもすでに数を減らしていた。

Google Pixel 5 / 下ノ大堀川
今回見たかったのはその対策現場。ミズバショウ群落と至仏山の撮影スポットである下ノ大堀川周辺を、ぐるりと防鹿柵..正確にはネット..で囲んだという話を聞いていたから。
高さ自体はこちらの背丈より低いので、この程度の柵はシカが本気を出せば飛び越えるのは簡単だが、ポイントは堀に沿って設置してある点だろう。この状況だと多くのシカは飛び越えるのは躊躇するはずである。

OM-D E-M1 MarkIII / M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO / ミツガシワ
その下ノ大堀川で見られたミツガシワの群落。この10年のスパンだと、例えそこが木道沿いで人の往来があるところでもこのような群落は壊滅状態だったので、明らかに柵の効果が出ていると考えられる。
竜宮周辺にも同様の柵が掘りに沿って施してあったので、またキスゲの季節に確認に足を運んで確認したい。
OM-D E-M1 MarkIII / M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO / コバイケイソウ
シカの食べ物という視点だと、コバイケイソウはシカが好まない毒があるので食害自体はない。ただ、年によって当たり外れがあるが、その点は今年は当たり年なのかな。
OM-D E-M1 MarkIII / M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
狭間の閑散期だったが、奇跡的に前幕の主役であるミズバショウ(写真左)と、次幕の主役であるニッコウキスゲ(写真右)を確認できた。
特にニッコウキスゲは木道沿いではこの1本だけだった。もちろんシーズンはまだちょっと先であるが。

Google Pixel 5 / 富士見田代から燧ヶ岳を望む
閑散期とは言えすれ違う度に受ける挨拶攻撃..時期が時期なんだから少しは考えろよって感じ..には閉口していたので、帰路は竜宮十字路から富士見峠を経てアヤメ平を周ってきた。
しかし、この尾瀬ヶ原(約1400m)からアヤメ平(中原山で約1970m)は富士見峠を経由するとその標高差は600m近くあって、平らなトレッキングコースと思われがちな尾瀬にあって、実はなかなか気合の入るコースである。
鳩待峠から至仏山が標高差で約630mなんで数字的にはそう大差ない。まあ実際の直登は300m程度ではあるが。

iPhone SE / 至仏山を正面に横田代を征く
尾瀬も全体的に設備が色々整備され、竜宮と富士見峠間にも昔はなかった木道があって驚いた。その分、鳩待峠・富士見峠間の整備が放置されているようで気になる。
アヤメ平は尾瀬ヶ原ほど人気がないのでシーズン中でも人はまばらだが、こういうご時世なんでいつ人出が溢れるかわからない。昔のように踏み荒らされる前に木道の整備は急務だろうね。