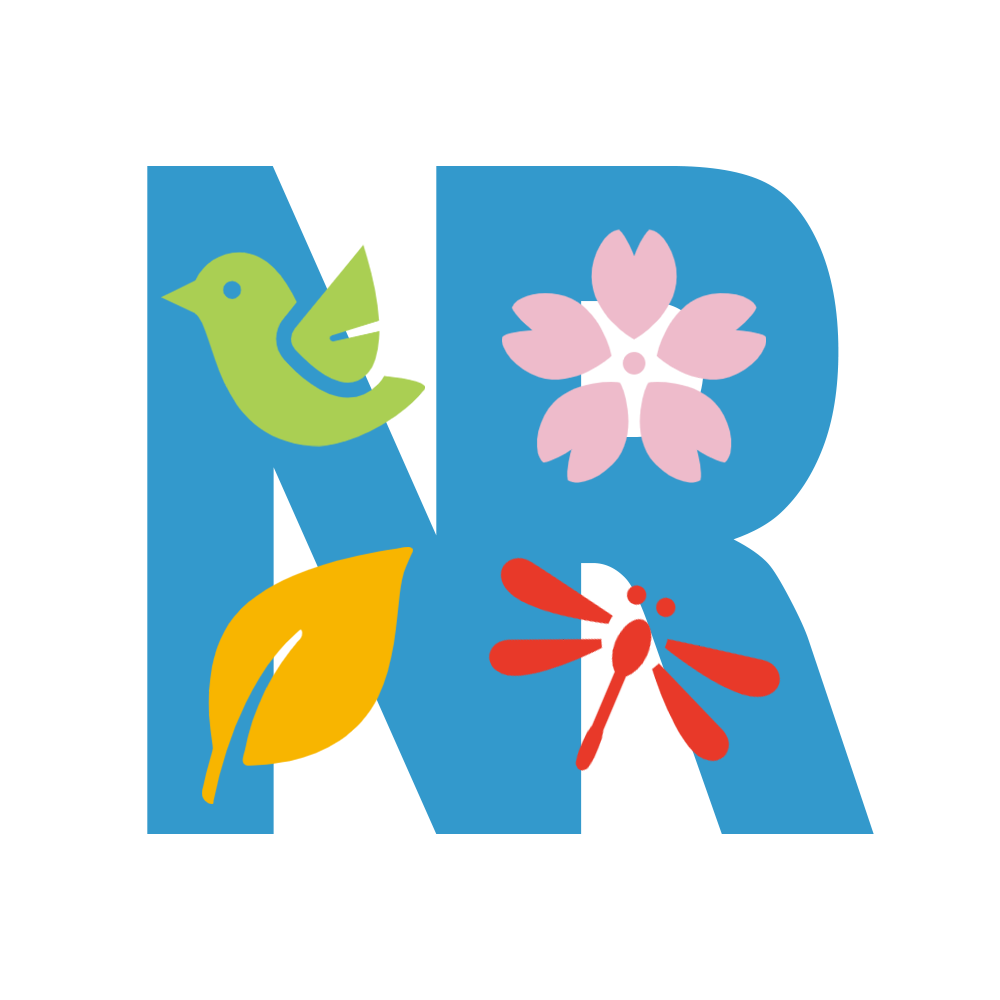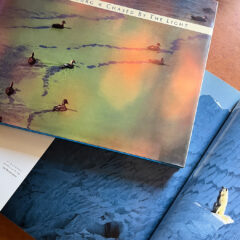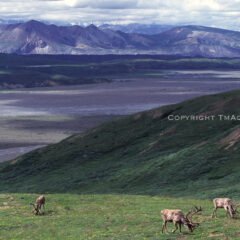プライスレスなのは本人の気持ちだけ
フリーで仕事していると無償や値引きを公然と要求されることがあるが、何か志しがあってやっているのだから無償奉仕的な精神論などクソくらえである。
例えば写真や映像なら、自然の中で写真を撮ることがプライスレスなのは撮っている本人の気持ちだけで、成果物をタダ貸せだ他人様に言われる筋合いは1mmもないぞ。
写真や映像でそれを平然と要求してくるメディアや自治体は結構多い..多いのはただで宣伝してやる的なアレね..ので、それが面倒でストックフォトサービスを立ち上げて運営している。
今どきはSNSを探せばただで写真を提供する輩はいくらでもいるので、そういう向きはそっちで探してくれって話。但し、著作や出処の保証はない可能性もあるけどね。
システム開発やWeb制作などIT系だと、「今回は安くして次回また仕事出すから」的なヤツも結構ある。若い頃は仕事欲しさに対応したことは何度もあるが、そういう案件に限って次があった試しはないので、今は絶対に引き受けない。
相手を下に見て無償や値切りをしてくる輩は、おのれが適正な価格で仕事を取れてないことの裏返し、つまり自身の無能さの現れでもあるので、そこはよく肝に銘じたほうがよいぞ。
それでも例外はあって、こちらがその理念に共感できたり、長い目で見てメリットがあると判断できれば無償対応も無いわけではない。
が、足元を見てくるヤツは長年の嗅覚ですぐわかるので、そういう手合いは門前払いである。こちらも伊達に長くフリーランス稼業で世の中を渡っているわけではないのでね。
まあ顔を洗っておととい来やがれって感じだなw