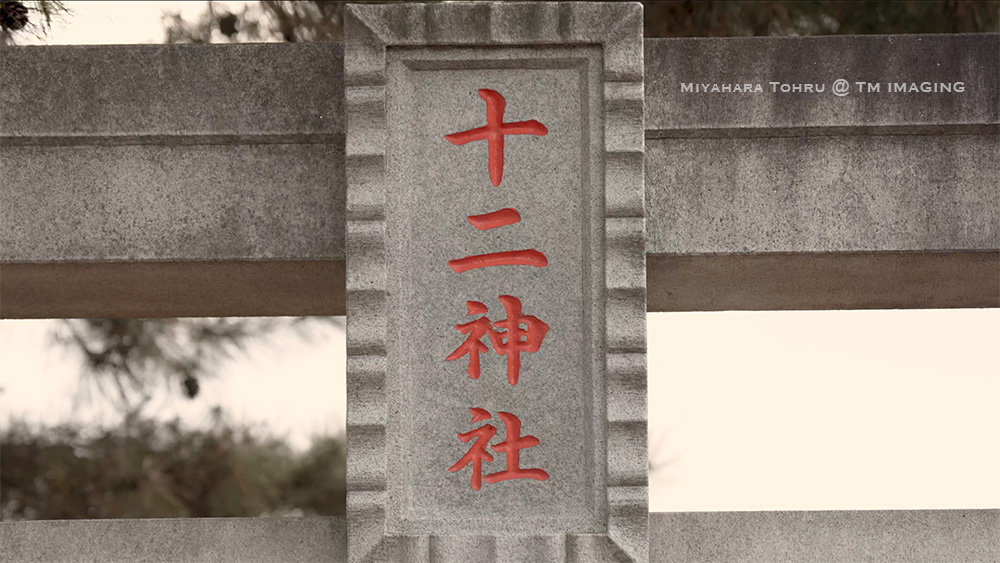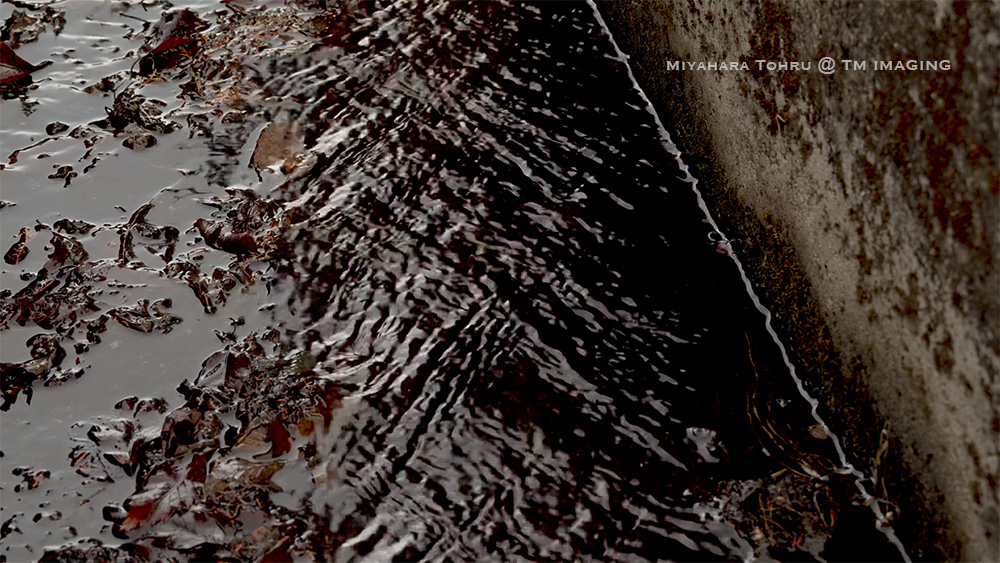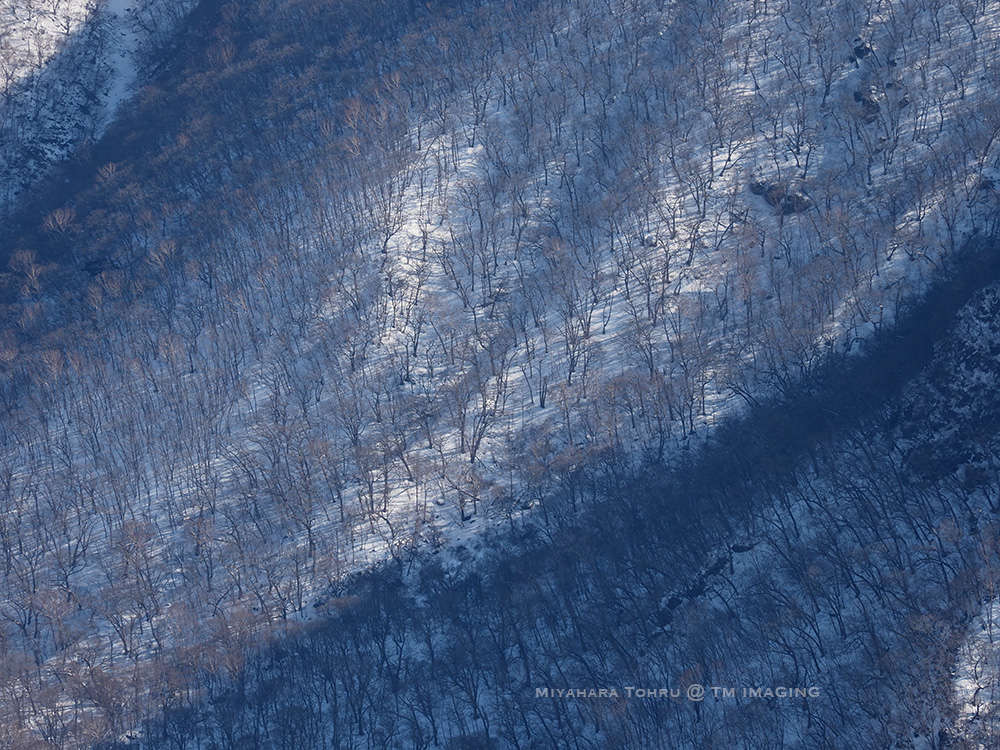コンピュテーショナルフォトグラフィ
先日はOM-1の2000万画素を「少ない」と書いたが、それはあくまでマーケットでの一般的な反応であって、個人的には2000万画素でも必要十分だと思っている。
カメクラ界隈で画素数を気にする人が多いのは承知しているが、現実的に2000万を超える画素数などまったく必要としていないというのは、GFX100Sで1億画素の画像を得られる立場にあっても変わらない意見である。
納品の成果物としてみれば1億画素で撮ったと言えば喜ぶクライアントがいるのは確かだが、実際に印刷物となるレベルなら1000万画素でも問題ないし、それがWebならば尚更である。
まあこの手の話は現実を知らない大きなセンサー&多画素絶対主義的な輩には通じないのであるが、そういう連中に限ってインスタなどSNSにアップして喜んでいたりするので、結構根が深い話ではあるわけだが..
マイクロフォーサーズはセンサーサイズが小さいが故に、画素数を増やすと高感度でノイズが増えると言う問題を孕んでいるのは現在でもそう変わらずである。
それにそもそもセンサーはソニーなどの外販頼りなので、多画素仕様のセンサーが出てこない限りはどうにもしようがないと言う問題もあるしね。
そこで複数の画像を同時に撮影、それらを少しずつずらしてコンポジットして画素数を増やすハイレゾショットなる機能を用意しており、さらにOM-Dの場合は手持ちハイレゾ(5000万画素相当)なる飛び道具まで搭載している。
この手持ちハイレゾは強力な手ぶれ補正を持つOM-Dならではと言え、前モデルのE-M1Mk3やE-M1Xにも搭載されており、マイクロフォーサーズで5000万画素のデータが得られるのは便利だったので多用していたが、カメラ内で撮影後に合成する都合上処理に15秒以上掛かっていたのがネックだった。
それがOM-1では5秒程度まで大幅に短縮され、ありがたいことこの上ないのである。
ハイレゾと似たような技術を使っている機能に、手前から奥までピンをずらしながら撮影して被写界深度内に収まっているかのようにコンポジットする深度合成がある。
ハイレゾと違ってレンズの収差が影響する関係上純正レンズしか対応していないが、一連の処理がカメラ内で完結するためこちらもよく利用しており、この深度合成にかかる時間も半分程度に短縮されている。
この他、スローシャッター効果のライブND、比較明合成のライブコンポジット、HDRなど本来PC上でPhotoshopなど使って実現するような画像処理をカメラ内で完結できる機能を、OM-1からコンピュテーショナル フォトグラフィと名付けてメニュー上で一箇所に集めており、今後はこれらを前面に押し出していく算段のようである。
実は初めてE-M1Xを使った時、こんな便利な機能をなんでもっと宣伝しないのか不思議でならなかったが、OM-1からそこを訴求していくマーケに変わったのは良いことである。
写真の世界でいう合成という言葉にはあまり良いイメージがないのも事実だが、まったく異なる状況の絵面を張り合わせたいわゆるインチキとは異なる性質の合成なので、スマホがすでにそういう方向性であるように、最初からデジタルデータなのだからカメラ内できることは全部やってしまって構わないし、個人的にはデジタルカメラとはそうあるべきだと考えている。
ということで話を画素数に戻すが、2000万画素程度に抑えているからこそのコンピュテーショナルフォトグラフィとも言え、恐らくこれ以上の多画素ではまたカメラ内での処理に時間を取られてしまうので、そういう意味でもこのくらいで十分という考え方になろうか。