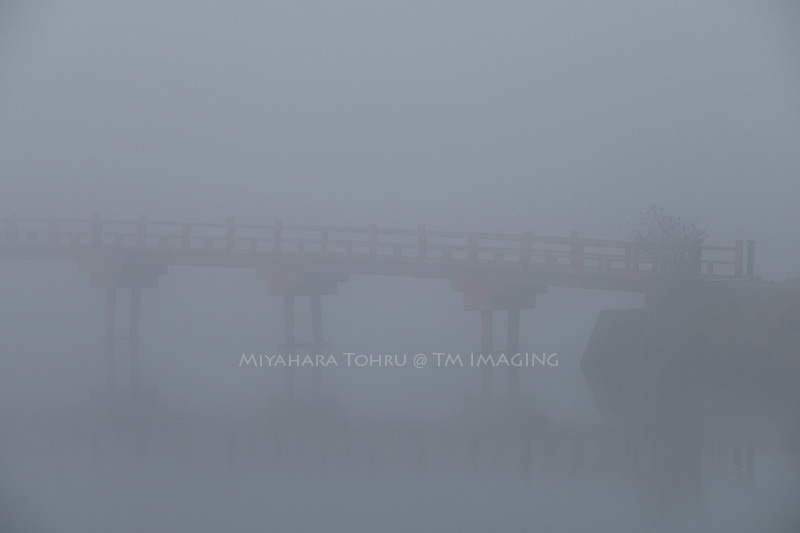先日ノビタキが通過していったので、次はエゾビタキの番だろうと思っていたところ、先日の台風24号が一過となった翌日に姿を見せた。

LUMIX G9 PRO / LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.
名前のエゾとは蝦夷のことだが、日本では春秋の通過時に見られる旅鳥で、北海道はもちろん国内での繁殖例はない。主な繁殖地はカムチャッカやシベリアである。
春秋の通過時とは書いたが、北上と南下で移動コースを分けているのか、赤城高原では春に見かけることはあまりない。恐らく春は大陸を経由する個体が多いのではないだろうか。

LUMIX G9 PRO / LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.
よく似た同族にコサメビタキとサメビタキがいて、慣れないと見分けがつきにくいだろう。両種よりは一回り大きいが、野外でその差を見極めるのは難しい。
コサメビタキにはない胸から腹にかけての縦斑の有無が一番分かりやすい。そしてそれが明瞭か不明瞭かでサメビタキとも区別がつくが、縦斑が割と明瞭なサメビタキもいるので、最後は下尾筒の斑の有無が決め手となろうか。
LUMIX G9 PRO / LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.
旅の途上で立ち寄った個体が20羽近くいたようだが、なかなかこの数がまとまっているのも珍しい。皆で黒く熟したミズキの実に群がっていた。
コサメビタキもそうだが、キビタキやオオルリと違って意外に人を恐れない個体がいて、ゆっくり動けば結構な近さまで接近を許してくれる。
大砲レンズを三脚に据えてあたふたしていては微妙な動きもままならないが、強力な手ぶれ補正を積んだマイクロフォーサーズ機とコンパクトな超望遠レンズの組み合わせなら、容易にそんなことも実現できる。
2枚目の写真などは真下まで行って見上げで撮っている..確認のために下尾筒を写したかったので..が、こんな芸当は三脚に固定した大砲レンズでは無理である。ましてや各地で老害被害が著しい野鳥写真の世界に跋扈する魑魅魍魎ジジイなど、翌日腰痛に悩まされること請け合いだw
世の中右を向いても左を向いてもフルサイズ、フルサイズと大騒ぎだが、ことワイルドライフの分野では、防塵防滴と耐寒性に優れたマイクロフォーサーズ機が一番に理にかなっている。
パナは来春フルサイズ機を出すが、マイクロフォーサーズも続けると公言しているし、主幹であるオリンパスは今後もマイクロフォーサーズ主体で行くと明言している。
まずはそのオリンパスが来春予定していると言われる、動画にも強いと噂のプロ機の登場が楽しみである。