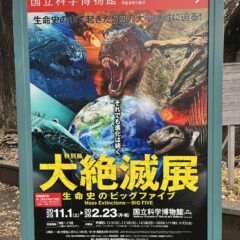鮮烈な紅
鮮烈な紅い実。おはようございます
#コマユミ
#OMSYSTEM
話題の #シビルウォー を観てきた。彼の国で内戦が起きたらという想定以外は争いの理由も何も説明が一切ない不思議な作品。胸糞悪いシーンが散りばめられているがBGMのセンスが良いのでジャーナリスト目線のロードムービーという仕上がりになっている。尚、戦っているのは恐らく州兵どうしと思われる
主人公の戦場カメ志望の若い女性がNikon FE2(フィルムカメラ)を使っていることに無理があるという意見があるが、使用しているのがモノクロで道中に簡易現像装置で現像するシーンもあり、最後の印画紙に徐々に定着していくかのような演出のためにわざとフィルムカメラを使わせたのではと勘ぐっている
良い兆しがということではなく、依然として危機的状況が続くという話で捉える必要がある。急激な個体数減は危うい
#イヌワシ
https://webun.jp/articles/-/690353
朝晩の気温が下がったので暖気中?足元にいるのに気が付かず危うく踏みそうになった。にしても近い。広角端の300mm側まで引いてさらに仰け反ってようやく画角に収まった
#キアゲハ
#OMSYSTEM
単焦点にするならゴーヨンのほうが売れそうだが今ひとつ踏み込めなかったか
https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/lenses/xf500mmf56-r-lm-ois-wr/
XF500は三脚座がアルカタイプのアリミゾ付きだがXF150-600と同じく相変わらず前後に貫通していない形状。ボディを装着すると後ろに重心が来るので前方にズラしてバランスを取ろうとするとクランプが噛んで傷が付くやつ。これ誰も指摘しないのかねぇ…
ひたすら木工に従事するITエンジニアを語るアカウントはこちら
#これもある意味個人開発