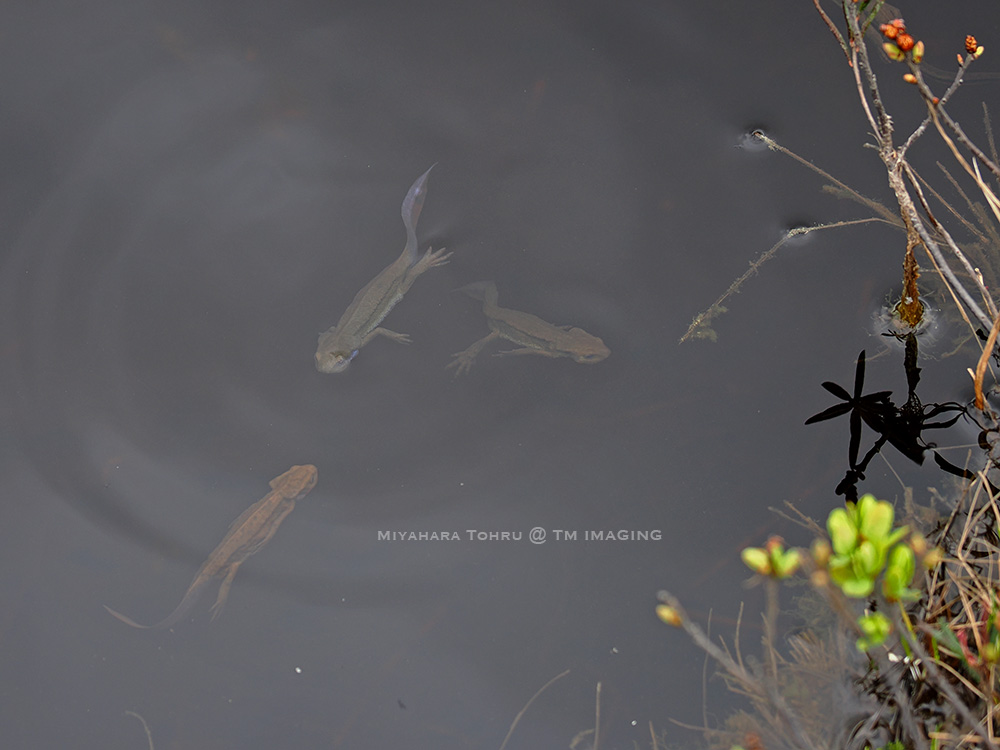キャリア両刀使い
先週末の au利用者は阿鼻叫喚だな。それほど今回の大規模通信障害の影響は大きい。
電話はともかくも、田舎住まいの拙者でもキャッシュレス化している..それでも現金は常に携行しているぞ..くらいなので、都会で日常をそれに慣らされている人はさぞかし大変だろう。
水道や電気同様にもはや携帯回線はインフラという位置づけなので、こんなIT後進国のニッポンであってもそこに付帯するサービスもすべからく全滅である。例えば気象庁のアメダスもau回線を使っていたようで、この猛暑の折りの重要な気象データが収集できないでいたようだ。
なので携帯回線の障害復旧もスピードの速さを求めらることになるが、今回のauの障害はちょっと遅過ぎだな。
ちなみに拙者はマルチSIM運用者なので、ドコモとauの両刀使いである。電話番号の関係でメインはドコモだが、バックアップを兼ねてauも契約して、常にフェールセーフに努めている。
稀に山間の過疎集落でドコモ回線が取れない地域があって、そういうエリアでも意外にauが入ったりすることもある..その逆もまた真なり..ので、そう言う意味でのバックアップでもある。
梅雨明け後しばらく好天続きだったが、昨日は久しぶりに夕立があって猛暑も一段落である。
台風が近づいているが、西日本では懸念通り早くも水不足のところがあるようなので、恵みの雨となることを期待したいね。