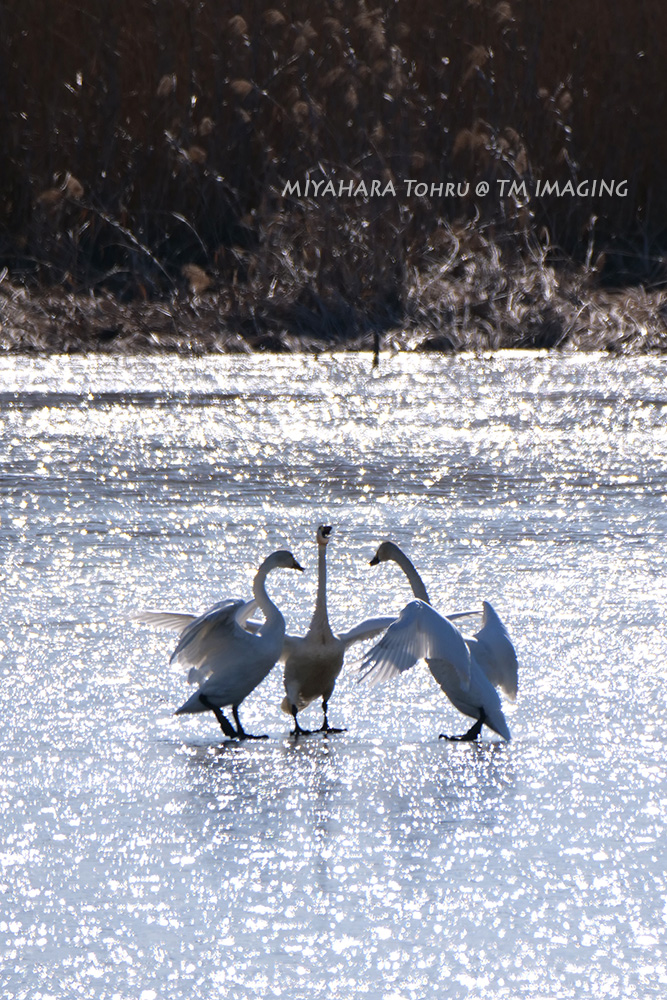X-H1の評価にAF性能の向上が挙げられる。関連してネットではAFスピードが早くなったというのがあるが、個人的にはそこを感じることはない。そもそもフジも公式でアナウンスしている通り、AFの測距スピードはX-T2と変わらない。
ただ、体感的に早くなったというのは確かにある。正確には早くなったのではなく、迷いが減ったという点だろう。そして恐らくそれが最もAFの良し悪しに繋がるのである。
目に見えてAFが迷う状況ということは、測距開始から合焦まで実測でも時間がかかっているということである。
EOSの頃からそうだが、AF測距点は個人的にはほぼ中央の一択である(ただし開けた空間を除いて)。そうなると、被写体を常に中央に捉えておけばよいという理屈になるのだが、XF100-400のような大柄なレンズを付けたX-T2でピンポイントで中央1点に合わせ続けるのは、特にAF測距点を狭くしている関係もあってなかなか難易度は高い。
そしてその理由は単純な話で、フロントヘビーの状態で取っ掛かりの少ない小さなボディを安定して保持するのは、結構至難の業なのである。
確固たる目的を持って木々の中を移動してくるヤマガラは、先日のエナガ同様に右に左にと常に動き回っていて、ファインダーで捕捉し続けるのは難しい被写体だ。
ピントを合わせたい場所は当然目(もしくは顔)になるが、そこに中央1点の小さな測距点を合わせ続けるのに、フラフラとカメラを構えていては撮れるものも撮れない。
今回X-H1では大型のしっかり握れるグリップの装備と、剛性感のある頑強なボディとなったが、こういったシーンではその恩恵は計り知れない。
メインとなる被写体とレンズの間に障害物..ここでは小枝だが意外にこれが侮れない..を挟んだ際、ちょっとでもAFを引っ掛けると見事に手前にピンが来るものだ。不意に手前に横切る物体を検知しても、AFが我慢する設定というのがX-T2にもあるが、問題はそこからのリカバリーの速さである。
AFが早く戻ればそれだけシャッターチャンスが増えるわけで、その点でX-H1はX-T2より明らかに復帰が早い。恐らくこういった地味だが堅実な性能向上が、AFスピードが早くなったという印象与えるのだろう。
小枝の隙間からほんの少しだけフレーミングをずらし、ヤマガラが飛び立つ直前にシャッターを切る。こういった繊細な動きは、やはりガッチリとボディを掴むことで成立するのだ。
ただ、他所のメーカーでは当たり前のようなことが、フジのカメラではようやくX-H1からできるようになったという見方もある。それは従来のフジのマーケットでは重要視されてこなかったからに他ならないが、X-H1の登場でいよいよフジもターゲットを外へ広げようとしているということだ。
デザイン性を優先するならX-ProやX-T系がある。X-H1には是非スパルタンな撮影領域を極めて行って欲しい。