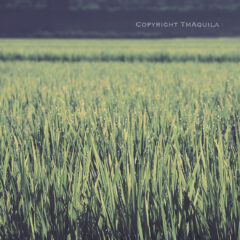昭和のITの終焉
富士通と聞いて、「フジツウさんに首を切られたマーティ」を想像するwのもすでに世代間ギャップを感じるものだが、その富士通が66年の歴史を持つメインフレームから撤退するというニュースを目にして、感慨深いものを感じるのも似たようなものか。
マーティの件の詳細はバック・トゥ・ザ・フューチャー2で検索してもらうとして、富士通がIBMなど黒船を相手に国内のメインフレーム市場を引っ張っていたのは事実なわけで、そのしんがりがいよいよ完全撤退するという。
顧客の保守の関係で実際は2030年度末ということなのでまだ時間は少し残っているが、細々とその分野で生き延びてきた昭和のITエンジニアも終焉ということになろう。
その昭和のITエンジニアの端くれたる拙者も、今や掌に収まる高性能コンピュータと言っても過言でないスマホのアプリ開発などしているわけだが、オフィスの一角を埋め尽くす大型コンピュータの時代が過去のものとなる時代が、予想はできていたが実際に訪れようとしていることに、やはり多少の感慨を感じるということ。
写真はお馴染みの上越国境だが、ちょっと高いところから撮影しているので、いつもとはアングルが異なる。
それにしても三寒四温なので寒い日もまだあるとは思っていたが、今朝の寒気は特に強いな。2月も後半というのにまだ氷点下9℃まで下がるとは。