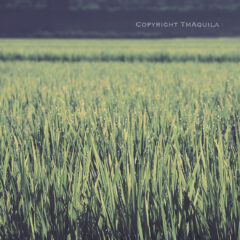さえずり飛翔
高速で飛ぶツバメの仲間を除けば、空抜けでゆっくり飛んでいる鳥は近頃の動物認識や被写体検出といったAI判定を頼らずとも、そう撮影自体は難しいものではない。
もちろん、それ以前に超望遠レンズでフレーミングできるかという問題はあるが..
AF駆動も位相差式であれコントラスト式であれ、画面内に他に目立つオブジェクトでもない限りはすぐに捕捉して追随してくれる。
春なので畑のあちこちでヒバリたちが終日賑やかである。ヒバリのさえずり飛翔は一見するとのんびり飛んでいるように見えるが、これが側から見ているより意外に難易度が高い。
似たような行動にカワセミの仲間や一部の猛禽類が行うホバリングがあるが、あれは空中一点にほぼ静止するため、シャッタースピードさえ早くすればそれなりに動きを止めることができる。
その点、ヒバリのさえずり飛翔は一見止まっているように見えても、高度が少しずつ変化する上に常時微妙に前後左右に動くため、AF-Cのようなモードであってもタイミングによっては微細な被写体ぶれが発生して、きっちり解像しないケースがある。
先日積層型センサーの高速読み出し云々を書いたが、データを素早く読み出した後、諸々演算後にバッファリングし書き出すという一連のシーケンスが素早く行われることになるので、それがローリングシャッター現象の軽減となって、結果的に解像寒の向上に起因していると思われる。
どんなに高速シャッターを切っても、データ処理の間..人の感覚など無縁の刹那だが..に被写体が動いてしまえばそれはそのまま被写体ぶれということになるので、いかに高速にデータを処理できるか否かが重要なのである。
と言うことでそのヒバリのさえずり飛翔を狙ってみたが、朝方のまだシャッタースピードを稼げずISO感度を上げるようなシーンで、例えばG9PRO辺りだとピンはくるが解像せずに輪郭が溶けてしまうような状況でも、OM-1はそれなりに解像している。
今回OM-1は従来機と同じ2000万画素に画素数を抑えてきたが、裏面照射積層型センサーを採用することで、その画素数の少ない点を逆手にとったスピードスター的なミラーレス機に仕上がっている感がある。