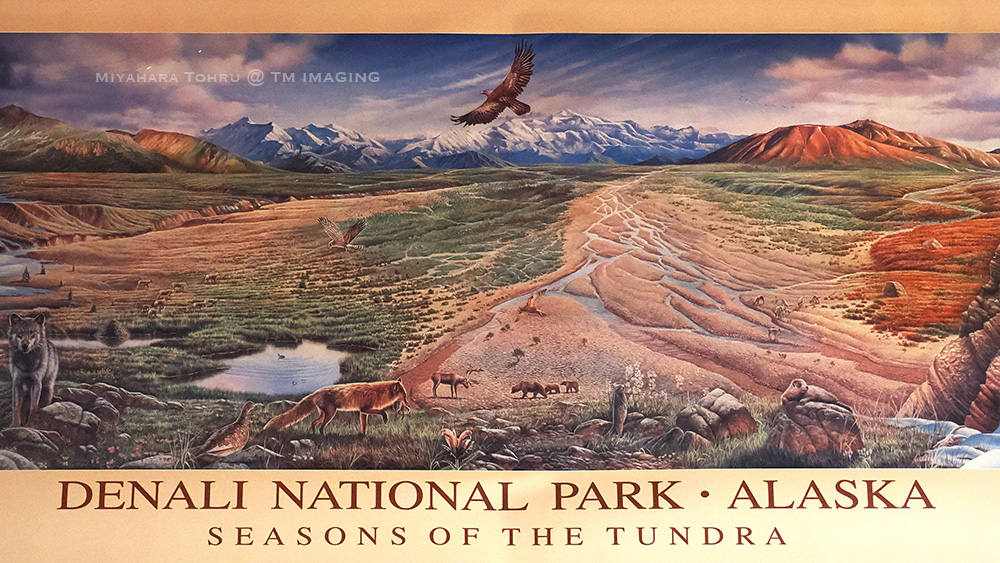話題の映画「トップガン マーヴェリック」をヒマを作って観てきた。もう上映開始3秒位ですでにサイコーって感じで、トニー・スコット風のシネマトーンを背景に、36年後に再びスクリーンでデンジャーゾーンを聴けるとは。2年待った甲斐があったなw
当時ブームを巻き起こしたカワサキGPZ900R(通称「NINJA」)をわざわざ登場させたのには感涙。ネタバレはご法度なので具体的な内容は控えねばならないが、予告編のアレが後半のまさかあの場面で使われるとはよもやよもやであった。
ヒマを作ってとは書いたが、実はGW明け以降毎週映画館に足を運んでおり、「シン・ウルトラマン」「ハガレン実写版」「マーヴェリック」そして今週は「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」。
庵野と樋口がタッグを組んだシン・ウルトラマンも文句なく面白かった。手書きのスペシウム光線に、特にメフィラス星人の山本耕史と巨大化した長澤まさみ..当時の櫻井浩子のオマージュ..が良かったなw
現代に寄せた設定の中で巨大な生物..劇中では禍威獣と表記..を人類が倒せているのにあまり無理がないのは、2016年に先行してシン・ゴジラを公開しているのが大きい。
特撮映画なので監督を樋口に任せ、編集を庵野が担当したのは理解できるが、一番受けたのはエンドロールでモーションアクターに庵野の名前があったことw これはテレ東で以前放送した「アオイホノオ」を観た人なら判るはずw
ハガレンは原作漫画が好きなのだが、一作目の酷さ..ジャニタレ主演というだけの理由で映画館では観ていない..にまさか続編が来るとは思ってもみなかったが、メフィラス星人、いや山本耕史のアレックス・ルイ・アームストロング観たさについつい足を運んでしまったw まあそのせい完結編も観なくてはならないハメに..
キング・ブラッドレイの舘ひろしなど脇のキャストは概ね同意できるのだが、主人公のジャニタレとウィンリィ役はやっぱりアウト。原作年齢が中学生くらいなのに30近い役者を当てんなよな。
でもこの原作年齢無視っていうのはゴールデンカムイの実写版でもあるんだろうなぁと今から憂鬱に。大人のアシリパさんなんて見たくないぞ..
「ククルス・ドアン」はなぜに今になってその回をリメイク?と思ったが、安彦監督曰く「当時忙しくて制作を外注に丸投げしたら見事に作画崩壊した」ということで、常に何とかしたかったという思いがあったとか。ただ、ドアンの搭乗する機体が作画崩壊した面長ザクをそのままというのは結果的にそのオマージュかw
冒頭のガンペリーからガンダムが起き上がるシーンは、サイド7で初めてアムロが搭乗して起き上がるシーンのオマージュだろうし、後半であのファースでおなじみのBGMが流れた時はグッとくるものがあった。
安彦監督はこれでガンダムに関わるのは終わりと言っていたが、周囲はやる気満々と思われ。興行成績次第だとは思うが、俗にファーストと呼ばれるガンダムについては、全話とは言わずとも安彦原作のオリジン版で作り直して欲しいね。

iPhone 13 mini

Google Pixel 5
スマホの写真でもシネマトーンに仕上げればそれっぽく見える。
とりあえずこの後は「大河への道」「流浪の月」「峠 最後のサムライ」と「キングダム2」「ジュラシック・ワールド」と続くかなぁ。
あと恐らくロングランになるだろうから「シン・ウルトラマン」と「トップガン マーヴェリック」は再度観に行きたい。