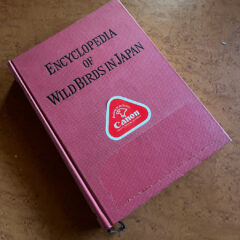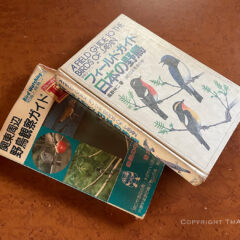4K、8Kと騒がれて久しいが、いつ頃世の中には普及するんだろうね、という話をよく聞かれる。この質問の真意はいつ頃「テレビ放送」されるのだろうか、という意味で概ね間違いないだろう。
が、そういう意味ではテレビ放送が2011年のFHD化(いわゆる地デジ化)のように、国策で一気に押し進むようになることはない無いと見て良い。少なくても私の世代が現役でそれを迎えることはない、というのが個人的な見解である。
私らは言わずと知れたテレビ世代であり、テレビ放送が国民的娯楽だった時代に観て育ってきている。が、インターネットが普及してから以降、何かコンテンツをモニターやスクリーンで愛でて楽しむという行為は、今やテレビという枠に囚われることなく、PCやスマホなどスマートデバイスに様々に広がっているのである。それが今日テレビ放送業界で嘆かれる、視聴者のテレビ離れの原因の一つに他ならない。
話を4Kに戻すが、面積比で2倍の4KはFHDの4倍の情報量を持つ。この膨大なデータ量を現在地デジに使われている通信帯域で出力する事は不可能なため、ここを解決するために国策の発動となるのだが、2011年の地デジ化でそれをやって国民に負担を敷いたばかりでまた同じことを行うのは、いかにも国民を愚弄するというもの。そこで業界こぞって期待するのが映像コンテンツ最大の祭典、東京五輪であろう。
ちなみでここ言う業界とはテレビ放送業界のことではなく、4K・8Kテレビを買って欲しいメーカー各社のことである。何しろ地デジ化特需の最大の恩恵を受けつつ、その後の買い控えの影響で業績不振に陥っているのはそのメーカー各社なのである。4Kテレビを何としても買って欲しい業界にとって、東京五輪は心待ちにするイベントなのだ。
が、その4K・8Kの普及で、一番被害を被るのはその為の過剰な設備投資を求められるテレビ局であり、テレビ離れがより深刻になると思われる未来において、どうしてそんな投資をしなければならないのだというのが本音だろう。テレビ放送が4Kになったからといって、視聴者が急にテレビの前に戻ってくるほど甘いものではない。見飽きたお笑い芸人の顔を高画質で観て何が楽しいというのだ。
つまり4K普及の鍵は、その高画質を活かせるコンテンツの提供にかかっているということだ。放送で流せない..一応、2020年迄のロードマップでは可能となっているが、それは対外的な問題である..となると、ではどこで4Kコンテンツを観るのかという話になるが、それが可能になるのはケーブルテレビやインターネットでのVODサービスが今のところ有力である。
VODとはビデオ・オン・デマンドのことで、試聴する側が観たいときにコンテンツを選んで観るというサービスのことである。BS波で放送している有料サービスのWOWOWなども、インターネット上でVODサービスを行っており、同様に既存のテレビ局でも少しずつ試行錯誤が始めっているところだ。
そして普及に向けたもう一つ鍵が、DVDやBlu-rayと同様のディスクメディア規格である「Ultra HD Blu-ray」だろう。前述のVODサービスがあれば十分だろうという向きもあろうが、金を払ったコンテンツを手元に置いておきたいという購買心理と同時に、通信帯域を気にせず本来の高画質を楽しめるという点では、Ultra HD Blu-rayに分がある。
もちろん、規格が決まってもそれ相当の優良コンテンツを提供できなければ後がないという点では、放送と同じであることは言うまでもないが。

7月に入ってからキジバトがヤマボウシで子育てを始めて、しばらく様子見..というか今回は意図的に無視していた..していたが、残念ながら今年も失敗に終わった。巣を造った枝も昨年とまったく同じ場所で心配していたが、今年もノラにやられたようである。雌が抱卵中に雄がよく家の前の電線で鳴いていたが、そういう行為を見逃さないのが野生の世界なのだろう。