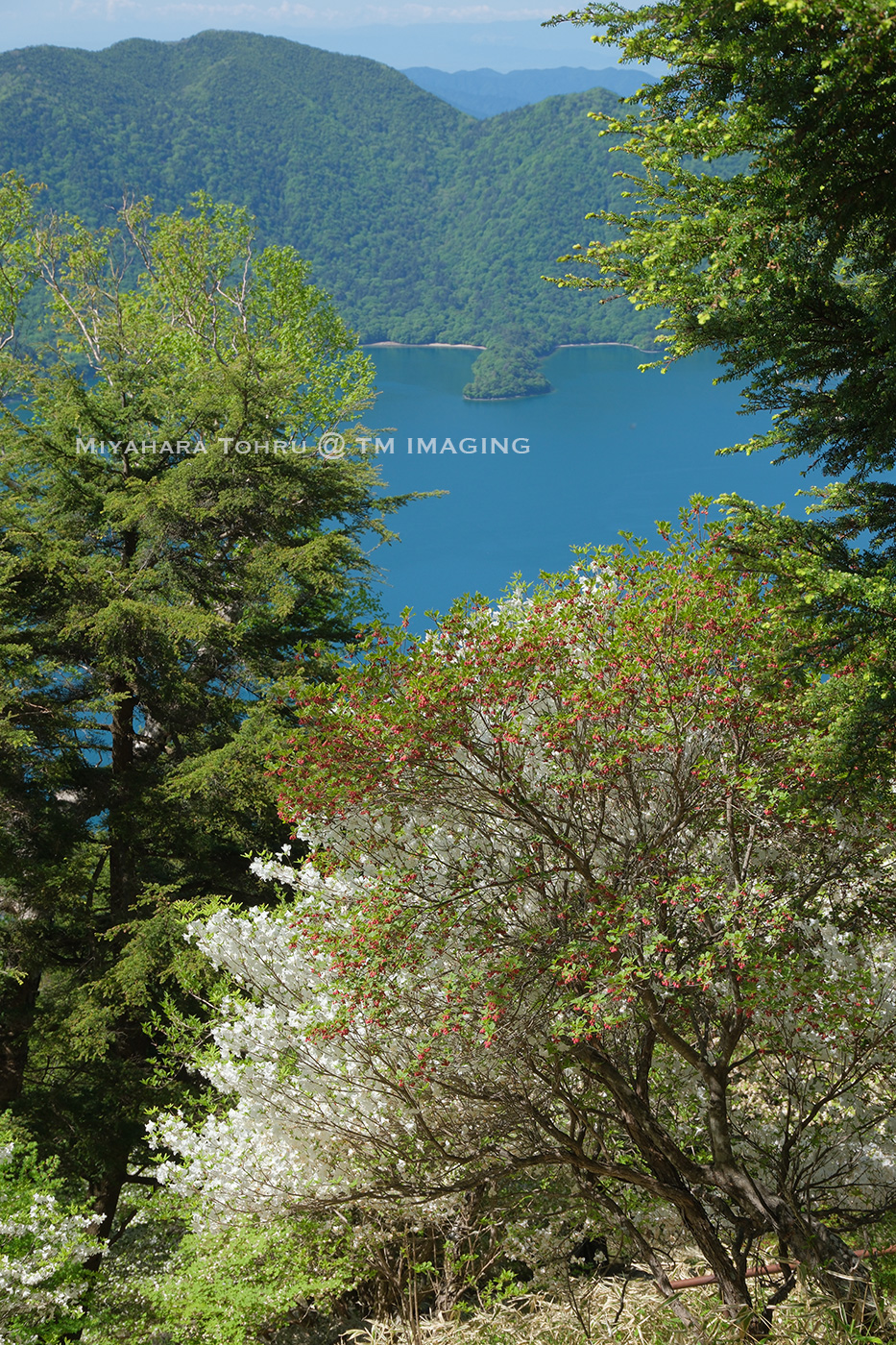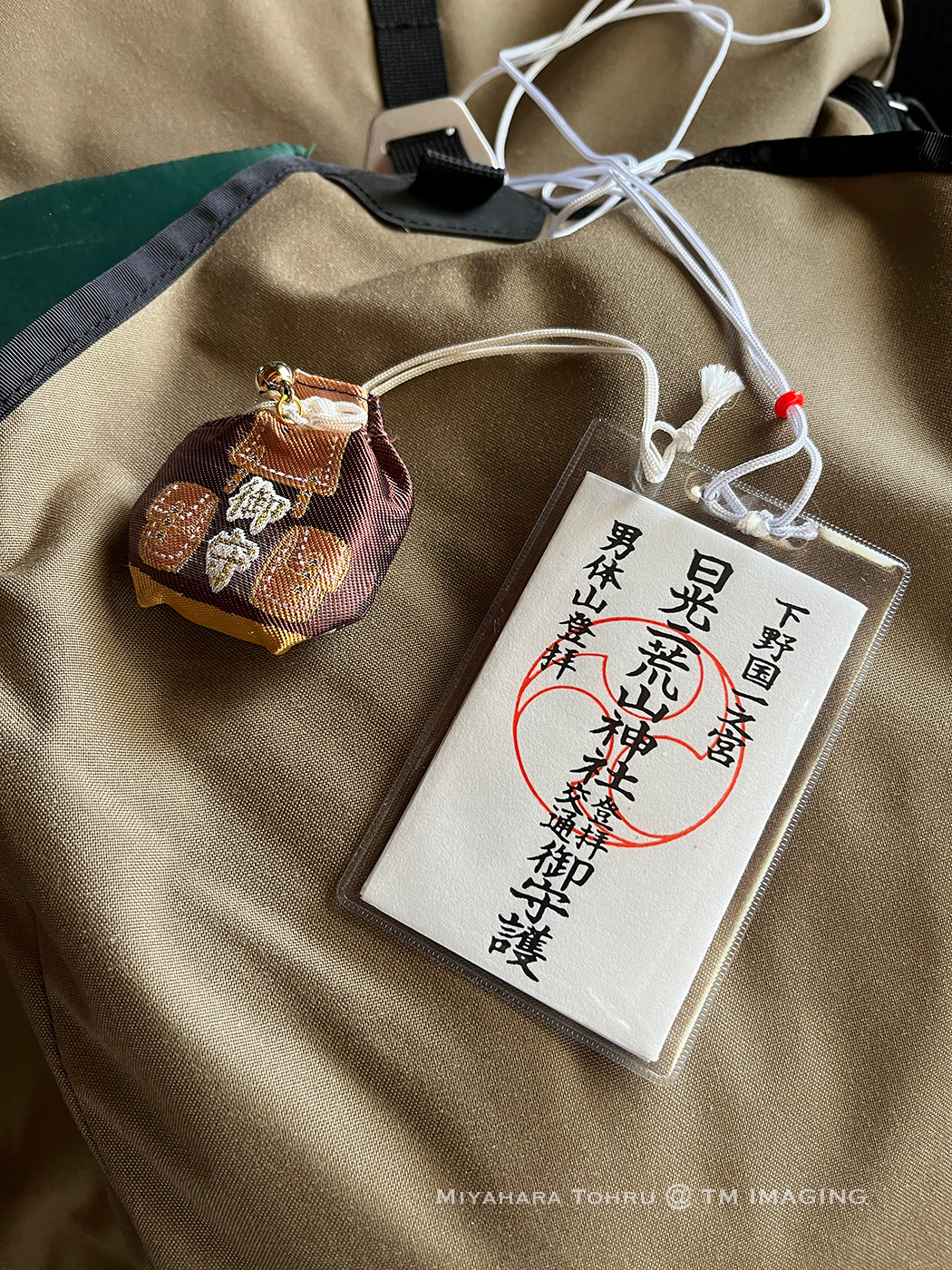一昨日の午後に久しぶりにゲリラ豪雨に見舞われた。言葉としてすでに定着した感があるゲリラ豪雨だが、意外に当地では数えるぐらいしか起きてなかった。
当日は朝からうだるような暑さで、午後には雷雨があるという予報だったので、昼前に草刈りを終えて昼飯食って昼寝をしていたところ、南西の空に怪しい雲が迫ってきているという家人に起こされた。

FUJIFILM X-H2 / XF8mmF3.5 R WR / Provia / パノラマ
写真を撮りに庭に出たが、雷雲はみるみる近づいてあっという間に土砂降りに。しかも小粒ながら雹まで降ってきて、家の屋根をガタガタ鳴らし始めたのには少々焦った。
が、豪雨は15分も続かずにあっという間に通り過ぎて行ってしまった。

FUJIFILM X-H2 / XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR / Velvia
夕立ちの後に夕焼けが広がるのはお決まりで、久しぶりにオキトマのスカイラインが夕景に映えた。
赤城高原の夕立ちは言葉とは違って夜半に来ることが多いので、午後遅くの雷雨は珍しい。ただ、この後は大気が急速に冷やされて素晴らしく過ごしやすい気温になったのは有り難い。これこそ夕立ちの恩恵である。

FUJIFILM X-H2 / XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR / PROVIA
で、昨日はその豪雨の名残で朝から湿気マシマシで湿度高く、沼田市街地は雲海の向こうとなった。