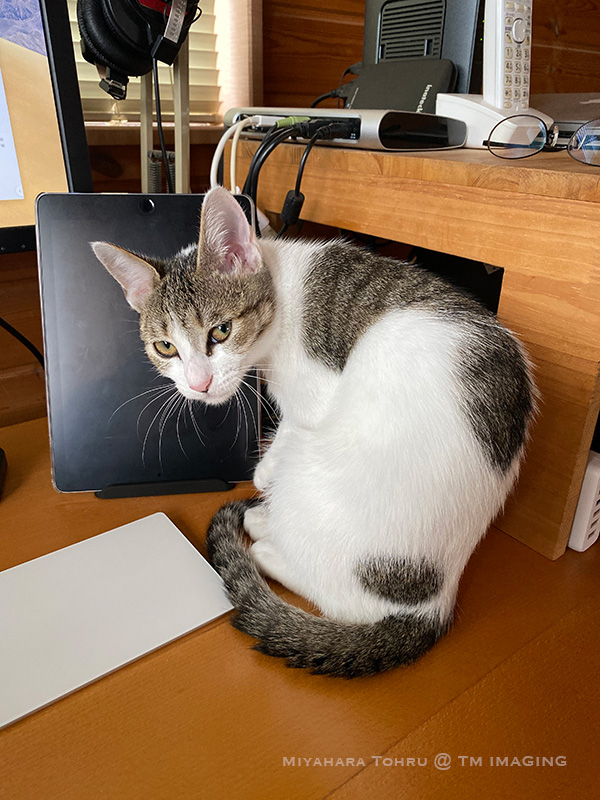雪の朝いの字いの字の蹄のあと
E-M1Xが業務用カメラとして有用な理由の一つはその防塵防滴性能だろう。
メーカーは一応IPX1まで保証としているが、プロモーション映像を見る限りそのレベルで収まる防滴構造でないことがよく分かる。
昨年の夏にスポーツイベントで夕立にやられたが、一時的とはいえ土砂降りの雨中で何の問題もなく使用できており、ほぼ防水と言っても差し支えない性能..あくまで個人的な判断..と見ている。
特にレンズ交換式カメラの場合、ボディだけで防滴構造は謳うことは叶わず、レンズ側にも相当の性能が必要になる。プロ用と言えば某C社のEOS-1D Xが挙げられるが、カタログで防塵防滴性能を謳うもIPXでは表示できないのはその辺の大人事情があるからだ。その点で、ED12-100PROやED300PROなどPROレンズを使う限り、E-M1Xの防滴性能は他社に比べても相当に高い。
実際のところ、企業向けのコマーシャル撮影を外ロケする時点で雨天となれば、それを意図しない限りわざわざ雨中での撮影続行は稀だが、スポーツでも観光でもイベントものは台風やゲリラ豪雨でもない限り催行されることが多いので、業務用機材の防滴性能が高いことに越したことはない。
以前、フィルム時代含め仕事はEOSを使っていて、正直なところ雨中で使用不可になったことはないのだが、この手のものは安心を買う保険のようなものなので、いかなる荒天下でも必ず撮れるという耐候性能はどんなに高くても困ることないのだ。
例年、積雪期になるとシカをほぼ見かけなくなるのだが、小雪の舞った朝早くにシカが歩いた跡が残っていた。そしてこれもまた暖冬の影響ということになろうか。
しかも猟期だと言うのに農道のど真ん中を悠然と歩いている辺り、実に堂々としたものである。まるで日の出前なら撃たれないことを承知しているかのような行動だ。