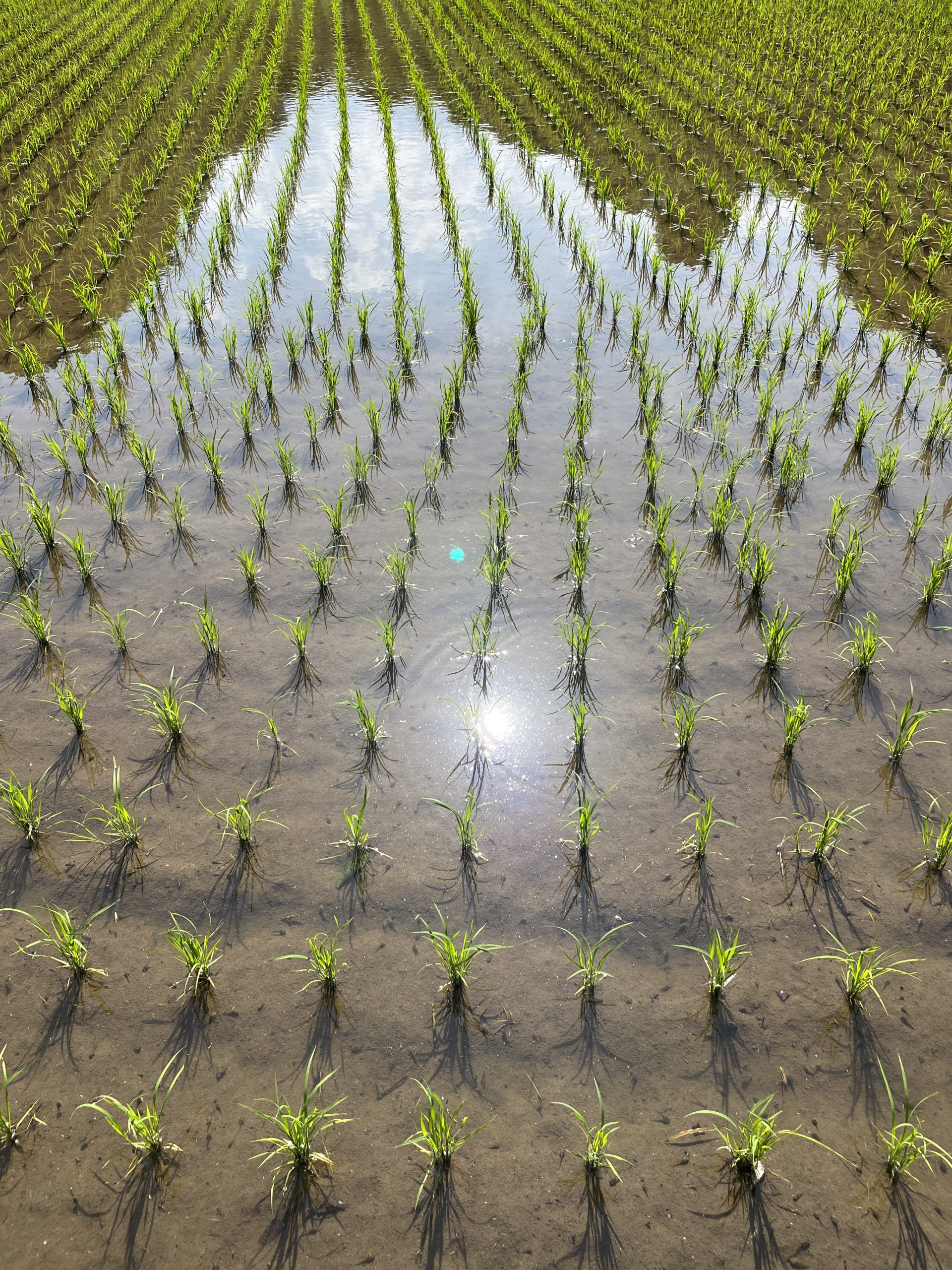1200mm超望遠マクロ
ちょっと前にOMDSから90mmマクロが発表された。マイクロフォーサーズなので35mm版換算で180mmとなるいわゆる望遠マクロであり、最大倍率は4倍まで拡大可能となる。
小生はそこまでマクロ撮影をすることはないので、さすがに17万をマクロレンズに払うことはないが、主なターゲットである虫屋や拡大精密写真など必要とする向きには歓迎される製品であろう。
以前、仕事で物撮りをしていたこともあるが、35mm版の50mmクラスのマクロレンズがあれば十分だったので、やはり専門性の高い分野向けと思われる。
ちなみに小生がマクロ的に撮るケースは、寄れる広角レンズで背景まで入れて接写する広角マクロか、超望遠レンズの近接による望遠マクロのどちらかである。
写真はシオヤトンボの雌(1枚目)と雄(2枚目)。何れも35mm版換算1200mm相当の超望遠マクロで迫った。
昆虫は反射的に忌避行動を取るので、どこまで近づけるかは経験則が物を言う。かくいう小生は虫屋ではないので大抵すぐに逃げられるけど。
雌はすぐに飛ばれてしまったが、雄は接近を許してくれたのでOM-1のカメラ内深度合成で全身にピンが来るよう撮ることが出来た。
何より1200mm手持ち撮影のこの近接で手ブレしないのはさすがのOM-1である。