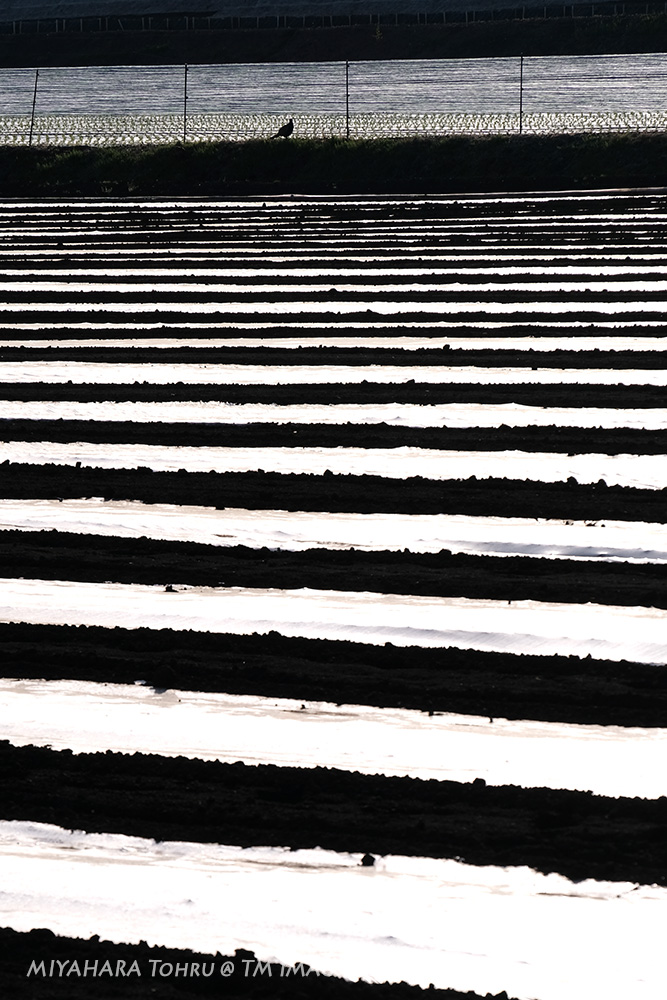先日デジタルカメラのファームアップの話を書いたが、ペンタことペンタックス(現リコー)が興味深いサービスを始めた。
それは「K-1アップグレードサービス」というもので、どうやらカメラ内の基盤を交換するという話である。PC的に言い換えればマザーボード交換とでも言うべきもので、ソフトウエアのファームアップではなくハードウェアの換装という荒業である。
作業的に当然ユーザー自身の手によるものでなく、ペンタのSC送りになるようだが、メーカーの手間暇は相当のものだろうと推察する。果たしてユーザー有料負担分だけでペイできるものなのか、何とも判断つかないサービスである。
面白いのは型番はIIと付く新モデル..K-1がK-1 MarkIIになるわけだ..なのに、製造番号は元のままという点。新モデルに中身は入れ替わるのに、修理扱い的なサービスであることは、SC対応であることからも判る。
もちろんこれがすべてのモデルで有効なのではなく、K-1に限ったものというマーケティングの側面を匂わせる部分があるが、それでも理由はともあれメーカーにしてみれば営業的には大英断だったろう。
そしてペンタついでではあるが、話の本題はこっち。現役プログラマーとして興味深かったのは、カメラを外部..USBまたはWi-Fiで..から制御するAPIをSDKとして公開するというサービスだ。
APIはアプリケーションプログラミングインタフェースのことで、ソフトウエアどうしが通信する手段を取り決めて公開するものだ。このAPIの仕様に基づき動作するソフトウエアを開発することで、外部からペンタのカメラを制御できるということを意味する。
スマートフォン用にはリコー謹製の純正アプリとして「Image Sync」というのが用意されているので、一般的にはそれで用は足りるはずだが、独自にカメラを制御できるアプリ開発が可能となれば、商業的に色々展開を考えられるのではないだろうか。
例えばInstagramにTwitter、Facebookなど複数のSNSと連携する場合、今なら個々のサービス毎にシェアするような作業が必要になるが、画像にクレジットを挿入しつつそれぞれに適切なフォーマットに変換してアップするというようなことが、一回の作業で完結できる..一旦自前のWebサービスを経由する必要はあるが..ようになる、などなど。
SDKはスマホ用にiOSとAndroidの他、PC向けに.NETとC++も用意するとのこと。このAPI公開は是非他のメーカーにも波及して欲しいね。ガラパゴス仕様はレンズマウントだけで結構だ。
LUMIX G9 PRO / LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.
ご近所コゲラはまだ抱卵中らしい。今日は餌を探しているオス..見えたら幸せの赤パッチが見える..を近くの雑木林で見かけた。
朝なので林内は陽も差さずに暗いのだが、G9 PROのAFはそこそこ食いついてくれている。ただ、少しでも測距点を外すとすぐに背景に持っていかれるのはパナのDFDの悪癖なので、このケースでは測距点のサイズをあまり小さくしないほうが良い。