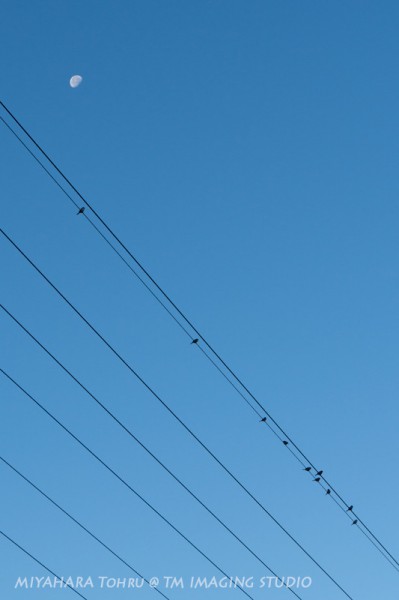カッコー鳴く
自分が聞いたのは今朝なのだが、家人は昨日の朝聞いたと言っているので、
今年の赤城高原への渡来日は21日ということなる。
音源が近かったので近くにいるとは思っていたが、
隣家との境に立っている電柱で2羽で争っているところだった。
ツツドリは早くて4月中旬、ジュウイチはGW頃には声を聞くようになる。
一番遅いのはホトトギスということになるが、
カッコウのほうが遅くやって来ることもあるので、
この辺りはどちらが早いという印象はない。
しかしこの5月は気温が安定しない。
相対的には寒いという感覚が強く、天狗様のエリアに足を延ばしても、
いつもならうるさいくらいのエゾハルゼミも静かなもんだ。
これだけでこの夏を占うのも何だとは思うが、
巷で言われるように今夏は久しぶりに冷たい夏なのかもしれない。