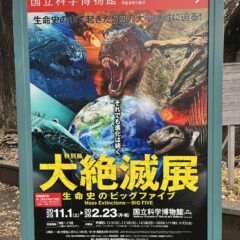星野道夫氏命日
走って転けて子ウサギの冒険。おはようございます
#トウホクノウサギ


昨晩は涼し過ぎて久しぶりに窓閉め切って寝た。今朝も涼しい高原の朝で、セミが鳴かない代わりにガビチョウがうるさい
Appleのティム・クックがトランプに尻尾を振っているとか一部に揶揄されているが、株主の利益や社員の雇用を守る為の企業トップの行動としてむしろ当然と思われるが。営利企業は行き過ぎた左翼思想を守る為に存在しているのではなかろう
フィールドでこの声は聞いたことが無い。餌乞コールだろうか。飛んでいる時や相方を呼んでいる時とは明らかに異なる。何にしても動物園ならではだね
https://x.com/moriokazoo/status/1953350144713474395
今日は写真家 #星野道夫 氏の命日。小生のような俗物が氏を語るなどおこがましいが、人や生きものは環境に生かされている、他の生きものの命を糧とし次の生命へ繋ぐ、という星野さんの自然観に深く影響を受けたのは間違いない。写真はアラスカのツンドラで夏草を食むカリブー。四半世紀ほど前の旅にて

そんなことだろうとは思っていたが何かもうめちゃくちゃ。日米修好通商条約じゃないんだからきっちりやってくれよ。お互い成熟した国家なんだし
https://x.com/nikkei/status/1953438826862362934
TLにハイタカ雌の写真が流れてきてコメントにオオタカって書いてあったので指摘しようと思ったが、トイレ入って出てきたらもう見つけられない。イーロン、おすすめ表示のアルゴリズム何とかしろ
国会議員時代はアベの子分を自認していたのででっきり石破をこき下ろすかと思ったが、意外にまともな意見で驚き
ただ、党内でそれ声高に叫んでいるのは大勲位のバカ孫だぞ。お膝元なんだから本人に直接言え
https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/737817
あまりにも涼し過ぎてセミも鳴かない
仏の保全計画の一環で、ピレネーのフランス側でボネリークマタカの繁殖ペア数が回復中とのこと
和名はクマタカと付くけど英名はBonelli’s eagle。Nisaetus属ではなくAquila属なのでイヌワシに近い。営巣も樹上ではなく崖地の岩棚で、狩場も草原や低灌木帯で生態もほぼワシだ
https://x.com/BirdGuides/status/1953379428194500878