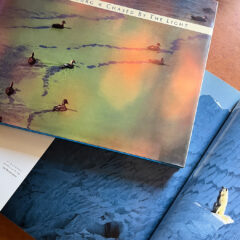ラスベガスで開催中のCESで、噂のあったソニーの民生用4Kハンディカムの発表があった。ハンディカムの名前の通り、FDR-AX100はすでに発売されているFDR-AX1よりも一回り以上小型で、4Kテレビの購入者、または購入を検討中の客層への訴求を狙ったものだろう。
ざっと情報をさらってみると、4KとはいってもDCI 4Kの4096×2160ではなく、放送規格であるUHDTVを見越しての3840×2160で、センサーサイズはAX1が1/2.3型800万画素であるのに対し、AX100は1.0型1420万画素だという。記録メディアは不明だが、4K30P(または24p)をXAVC Sで記録でき、フルHDへのダウンコンや、同MP4を同時記録もできるらしい。気になったのは4Kから指定範囲を2Kに切り出せる点だ。カメラ単体で実現できるとすれば、画質劣化のない2倍テレコンのようで面白い機能かもしれない。
しかし、業務用途で考えた場合、単純にカメラが小さければ良いというものでもなく、使い勝手など含めて評価されるべきだが、価格が2000ドル前後と聞けば、AX1に飛びついたユーザーの心中は穏やかではあるまい(笑)。
さて、メーカーがいくら4K、ヨンケーと騒いだとて、現状ではコンテンツが揃っていない上に、肝心の放送に関してはほとんど目処が立っていない状況にある。このままでは2020年の東京五輪を待たずして、3Dテレビと同じ憂き目に合うのは必定なのだ。試聴するコンテンツがない、それなら顧客自身に撮ってもらえば良い。可愛い我が子の運動会やお遊戯会など、従来のHD映像の置き換えを考えているのであろう。肝心の撮影後の保管方法などまだまだクリアすべき課題は多いが、4K元年を見据えたソニーの意地も垣間見える。

近所の畑に残されたノウサギの新旧足跡。以前にトラップカメラを仕掛けた際にはめったに写ることはなかったのだが、雪が降るとこうしてその存在を知ることができる。