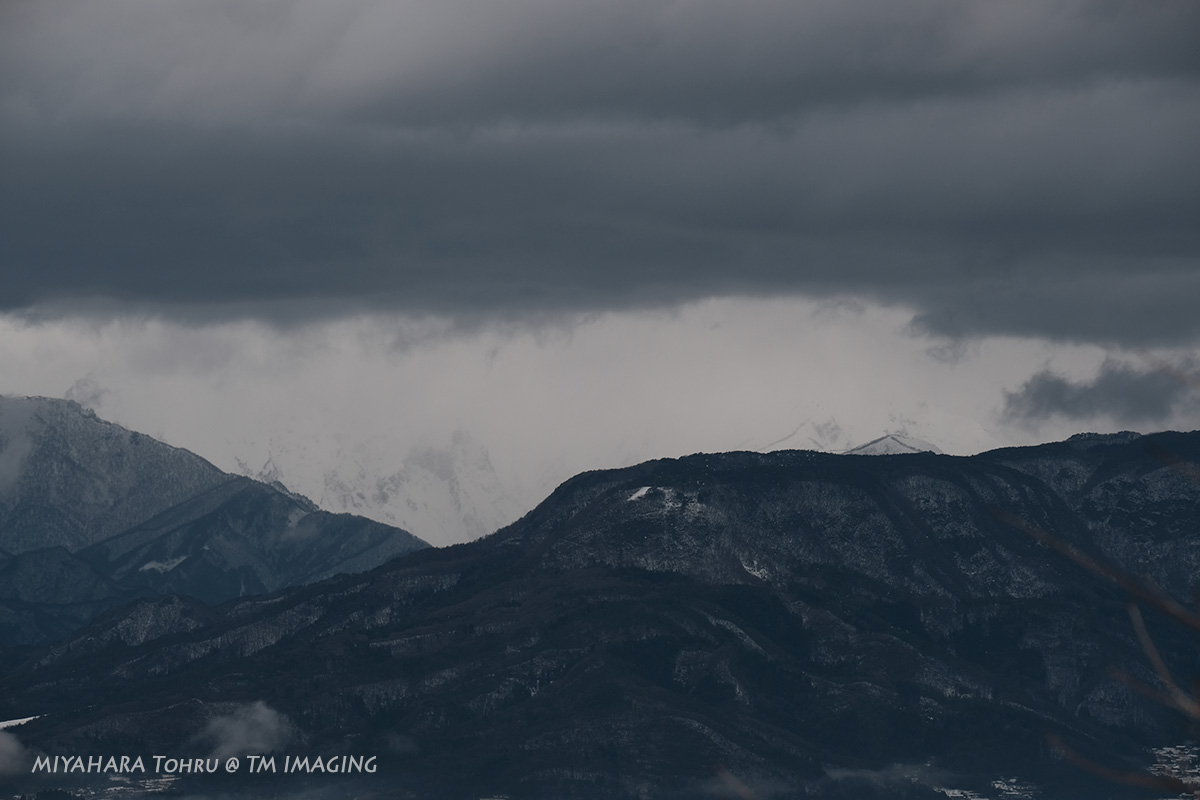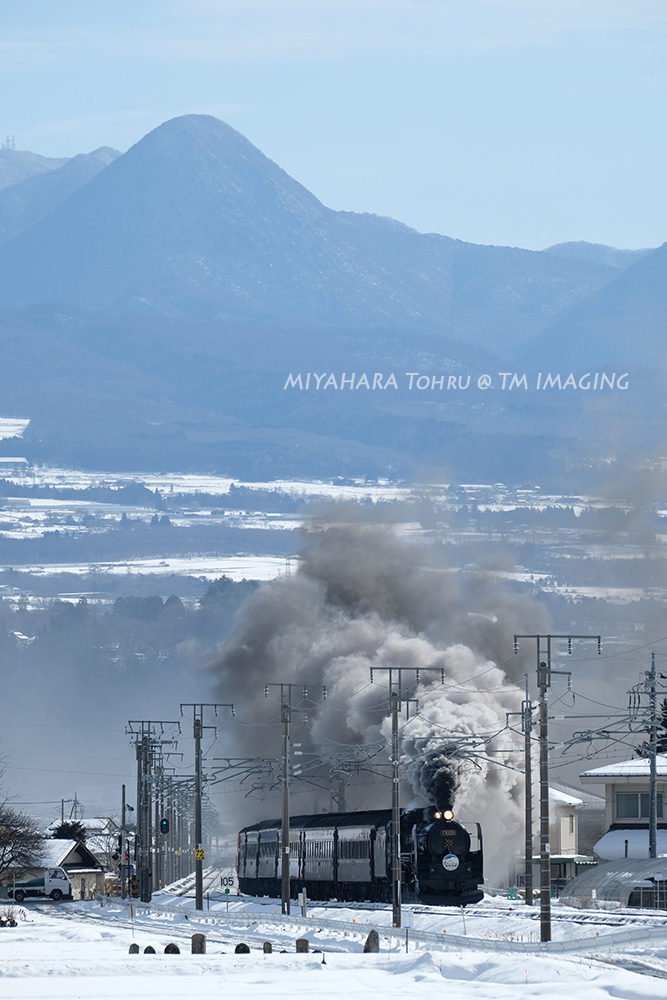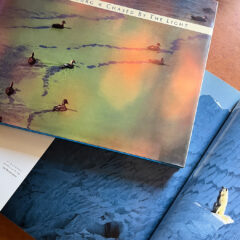撤退か勇退か、それが問題だ
かねてから業績がはかばかしくないと噂されてきたGoProだが、とうとうドローン分野では白旗を上げたようだ。
発表時は期待の高かった同社初のドローンKarmaも、発売時に重なったトラブルやリコール、何より業界の雄であるDJIのMavic Proに完全に食われてしまったのが痛かった。
確かにドローンの黎明期では、ブラシレスモーターのジンバルにGoProをぶら下げて撮影していた時期があったので、どうせなら機体そのものも自社でと夢見たのは理解できる。
が、そもそも小型のアクションカムと、ドローンの機体制御などはまったく別の技術なので、安易に参入を試みたのは米国的には「Nice Try」なんだろうけど、そこにはアメリカンドリームは無かったということだ。
大陸製、中華製などと揶揄される、安かろう悪かろうのいわゆるメイドインチャイナにおいて、DJIの技術力はかつてのモノ作り大国メイドインジャパンを彷彿とさせるものがある。誤解を恐れずに言えば、今の日本にはDJIに太刀打ちできるメーカーは存在しないだろう。たとえ技術力はあっても、それを製品としてキチッと市場に安定供給できなければ、絵に描いた餅である。
今後GoProは本業のアクションカムにリソースを注力していくと言っているが、その分野でも中華組の新興は目覚ましいので、それとてうかうかしてはいられないだろう。
ヒーフーヒーという素っ頓狂な鳴き声に振り向くと、イカルの群れが朝日を浴びて暖気中であった。比較的樹冠にいることが多いが、斜面の上部からならそういった梢が目線の高さになることもある。
イカルは通年家の周囲でも見かけるが、冬季と言えど餌台に寄ってくることはない。見るからに立派なくちばしでヒマワリの種は好きだとは思うが、群れているせいか総じて警戒心が強い鳥ではある。