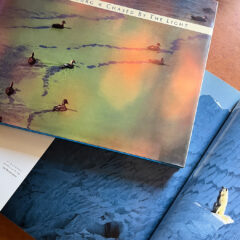黒鉄の城、その名はZ
世の中のニコ爺、いやカメラファンが待ちに待ったナイコン初のフルサイズミラーレス機が発表された。その名もNIKON Z。
拙者の世代では「ゼェェェェェェット」とつい叫んでしまうw、というどうでも良いことはさておき、またまた名前の付け方で迷走しそうな感じがしないでもないナイコンよ。
Z7とZ6はZ7のほうが上位機に当たるようだが、Z7程度の仕様ではとてもプロ用とは言えない。恐らくレンズが出揃う2020年以降にフラッグシップ機が登場..ナイコンは東京五輪はレフ機で勝負ということだ..するだろう。
問題はその名前だが、今までのナイコンであれば一桁機は1が最初だが、今回はなぜか6始まり。しかも上位機は数字が1つ多いという謎。もしかしたらソニーαに倣ってフラッグシップをZ9とかにして、次のモデルから某C社式にMarkxxを付けたりして。
ちなみに「Z7」ではなく「Z 7」だそうだ。お判りかな?にわかに信じられないことに、Zと7の間に空白があるのである。このネット検索のご時世に、そこに空白を空けるか!
試しに「Z 7」と「Z7」でググってみると良い。正式名より後者のほうがより上位に製品ページが並ぶはず。もちろんGoogleの検索結果は生きものだから日々変動していくものの、マーケ部隊の責任者って判ってやってんのかね、これ。っていう製品の本質とは違うところについつい目が言ってしまうのはWeb屋としての性なのさw
さて、はたしてNIKON Zはカメラ業界にそびえる黒鉄の城になれるか!って、しばらくこのZネタで遊べるw
空にそびえる黒鉄(くろがね)の城と言えばマジンガーZだが、現実の世界ではそこはやはりSLに敵うものはないだろう。漆黒の鉄の塊が疾走していく様は、重厚な走行音と共に力強く迫力がある。