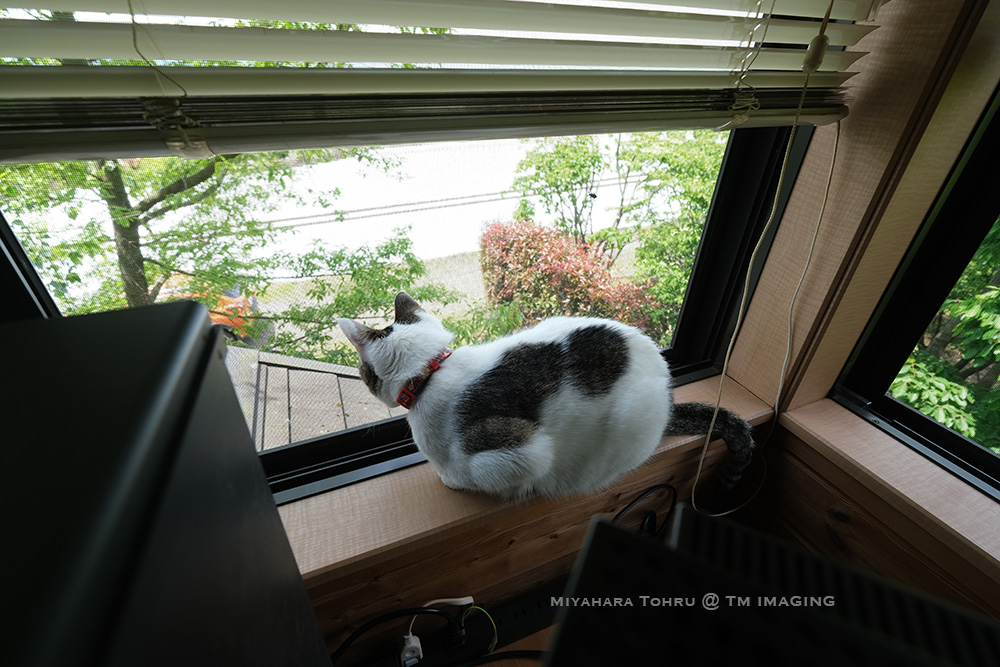休まず働け
アレの新コロナ対応で連続140日間執務にご苦労さまみたいなニュースを見かけたが、定額でも持続化でも必要な人に未だ行き届いていない中抜き給付金問題に日々呆れそして怒る国民が、ろくに仕事で結果も出せていない無能大臣をねぎらう言葉など持っていようか。
専門家会議には冒頭の数分程度写真撮影のためだけに顔出し。国会では野党議員の追求に意味不明のしどろもどろで対応。記者会見で国民に自身の声を届けることもなくひたすら官邸に籠もり続け、夕方になればさっさと隣の公邸に帰るだけ。
そして土日に公務と言っても小一時間程度官邸に顔を出すだけなのは、首相動静を見ていれば誰にでもわかることだ。
何よりD通疑獄とも揶揄される疑惑だらけの国会を早々に閉じてしまって、秋まで事実上の長期休暇ではないか。国民全員に給付金が届くまで、お前らが休んで良い理由などどこにもないぞ。
さらに自民党所属議員にはボーナスや歳費とは別に200万円もの現ナマが即刻口座に振り込まれたと聞けば、待てど暮らせど1ヶ月以上も10万円すら振り込みされない国民からみれば、何をふざけんなって話で感情の逆なでもいいところだ。
何れ取っても今詰めて仕事に明け暮れている風はない。そんなアレに「少し休んで欲しい」などとほざく取り巻き一派と、それを媚びを売るように報道するマスゴミにも辟易だぞ。
いいか、政治は結果が全てだ。一生懸命やってます感や言葉の自画自賛も賛美も無用。リゲイン飲んで24時間戦え。
近くの木の洞を巣にしているコムクドリ。夫婦でひっきりなしにそれこそ休みなく餌を運んでいる。
樹冠から降るようにエゾハルゼミが賑やかな林内だが、親鳥が巣に入ると雛たちの声も負けじと騒がしくなる。コムクドリはムクドリの仲間だけあって成鳥も良く鳴くが、雛の声もなかなか賑やかなものだ。