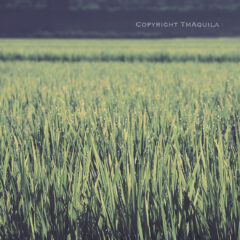2月のCP+で実機がお目見えしたパナのVARIO-ELMAR 100-400mm。望遠レンズの不足が指摘されるm4/3機において、オリのED 300mmと並んで世間の期待値が高いレンズであろう。

すでに発売されているが、受注生産というまか不思議なことになっているため、CP+で実物を見てから注文入れた人の手元に届くのは、早くても5月だろうと言われている。そんなに売れんだろうと見込んだパナの営業は明らかにリサーチ不足と言われても仕方ないが、なかなかよく作りこんだ造作をしているので、単純に生産数が少ないだけかもしれない。
いわゆる大口径レンズではないので、開放値は400mm側でF6.3と暗いのだが、動画屋としてはそこは問題ではない。どうせND付けて光量は落とさなければならないし、そもそも変にスペックにこだわられてガサが増えられても困るというものだ。
今どきのズームレンズなのでバリフォーカル..ズーム位置でピント面が移動する..なのはご愛嬌だが、その恩恵?で最短撮影距離が1.3mというのは良い。35mm換算なら撮影倍率は0.5倍と、ちょっとしたマクロ撮影にも使用できる。
ボディからレンズを外すこと無く三脚座を取り外せたり、AFが迷子になりやすいパナ機において、フォーカスリミッターがあるのもよい。
そしてこのレンズの真骨頂は、100-400mmというのは世を忍ぶ仮の姿?であり、35mm換算で実質的な焦点距離が200-800mmという点だ。画質面では専用の1.4xテレコンを付けてもオリの300mmのほうが良いのだが、全長が17cm足らずのレンズで800mmを手持ち撮影できる..こうなるとボディ内手ぶれ補正と併用できるDual I.S.のGX8が欲しいぞ..というのは、動画でワイルドライフを狙うものとしては、ズームレンズが便利なのは言うまでもない。
気になった点では、CP+で触ってきた人の話の通り、ズーム操作の異常なまでの硬さには閉口する。ストッパーが付いているのだからこの硬さは要らんだろうと思いつつも、この辺は使い込むうちにそれなりの操作感になるかもしれない。
それと、申し訳程度しか伸びない内蔵式のレンズフードの貧弱さは、哀れとしか言いようが無い(苦笑)。レンズ保護にもならないので、はっきり言ってこれなら無くてもよい。別売りでいいので、しっかりした外付けのフードを用意すべきだろう。


適当な被写体がないので、見頃を過ぎた梅を試写。赤城山麓では桜以前にまだ梅が咲いているのだ。
写りは値段なりで、逆光にもそれなりに耐性があるのは今どきのズームレンズと言ったところか。ま、至近距離でシャープなのはある意味当たり前で、望遠レンズの真価が問われるのはやはり遠景だろうが、それはまた次回。