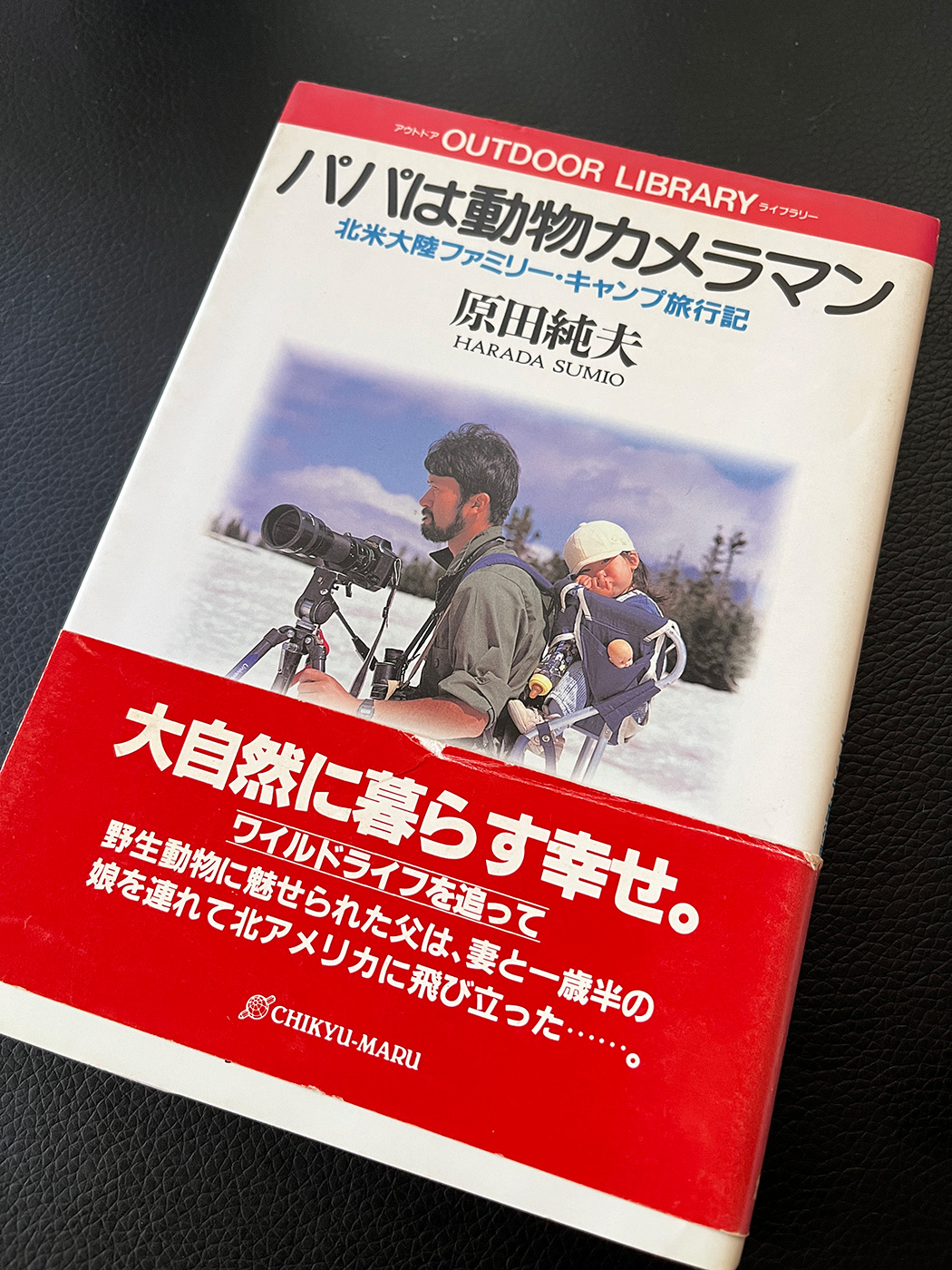ブルーマウンテンズ
ナンタイサーン!おはようございます
#男体山
#LUMIX
最初から取らなければ良かろう。無駄にコストも掛からん。そもそも野党のくせにジミンと同じこと考えるなよ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA07AH30X01C24A1000000/
北米ロッキーのマウンテンゴート(シロイワヤギ)と言えば原田純夫さん。これは楽しみ
https://www.nhk.jp/p/wildlife/ts/XQ57MQ59KW/episode/te/MPR2YW2LYZ/
原田氏の著作は何冊かあるがとにかく面白いのが本書。動物カメラマンを目指す思い切りと現実、家族愛など大変さが伝わってくる。写真家の故星野道夫氏との邂逅シーンもあって良き
ブルーマウンテンズ
#四阿山
#北アルプス
#LUMIX